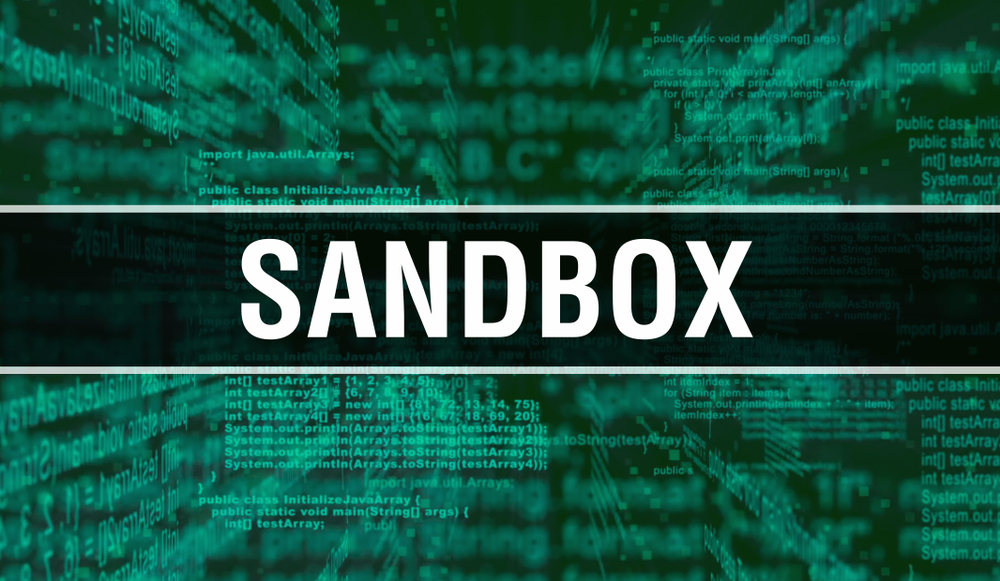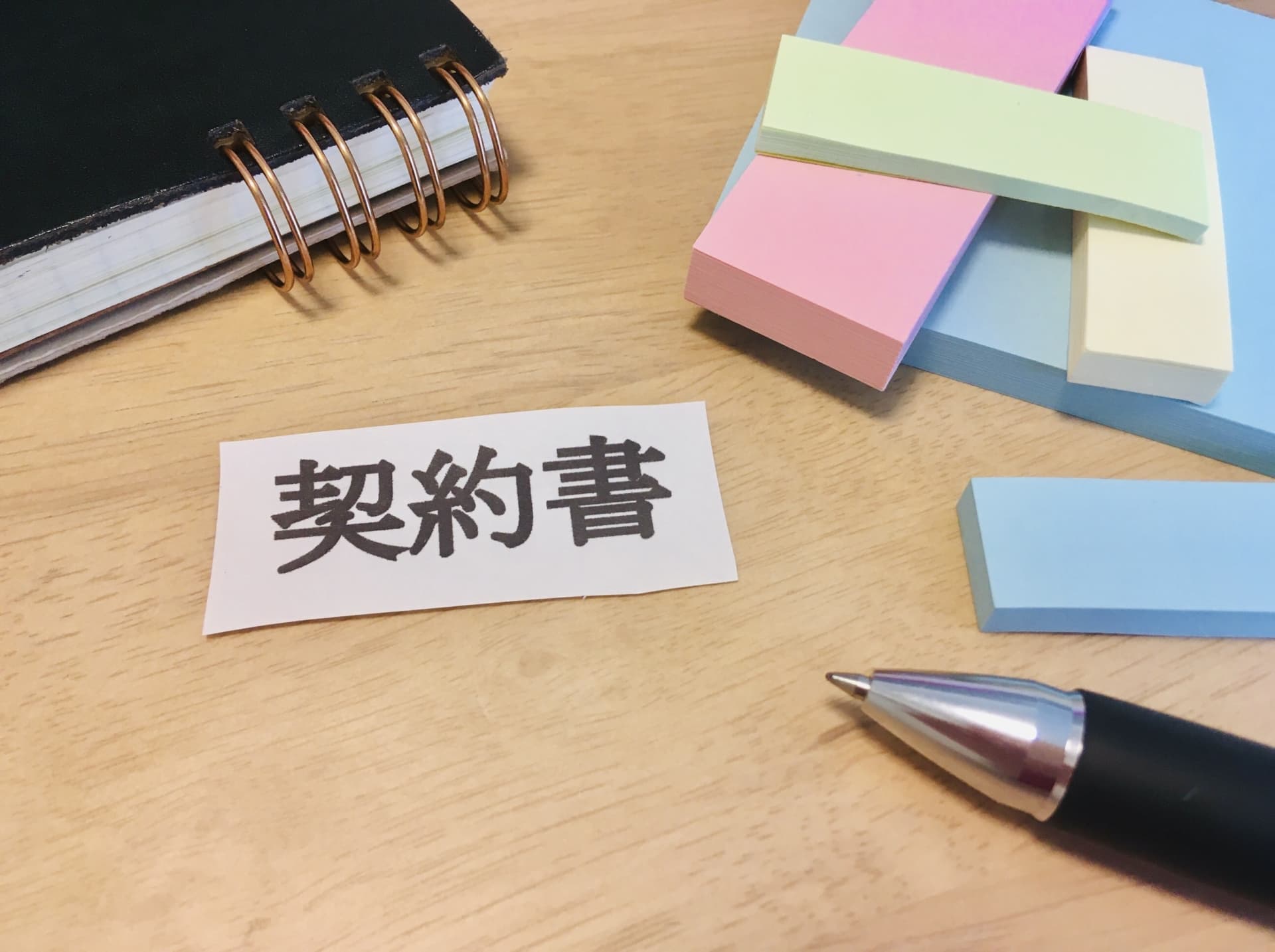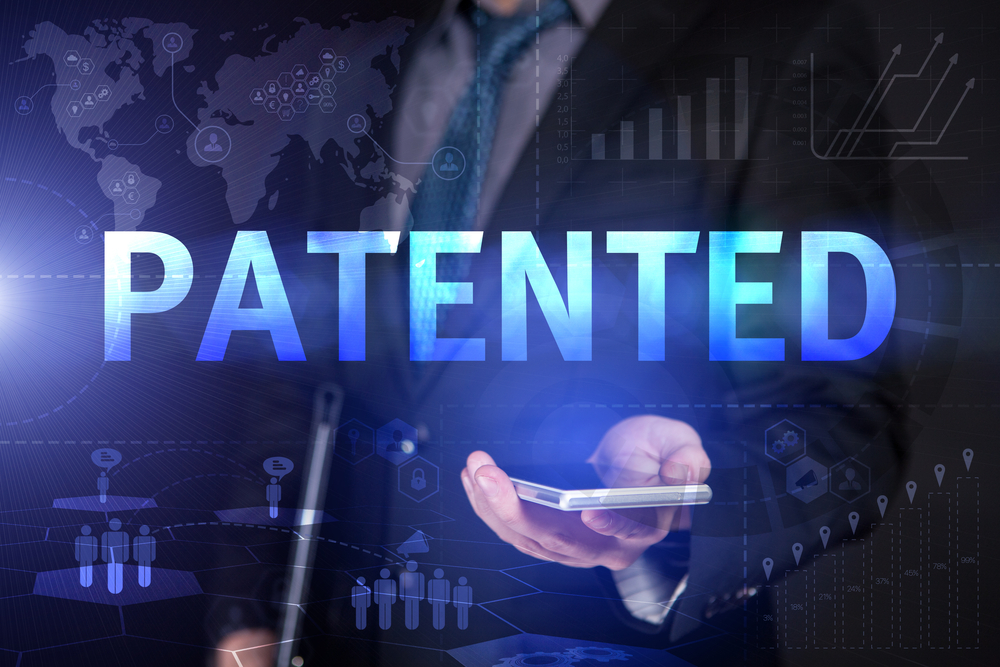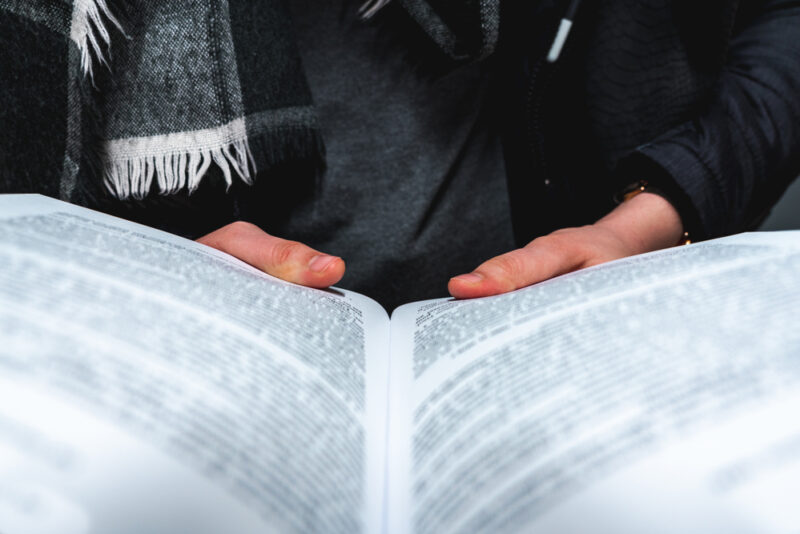社内資料の配布は著作権法違反?企業活動における著作物利用の基本とリスク(令和7年版)【チェックリスト付】
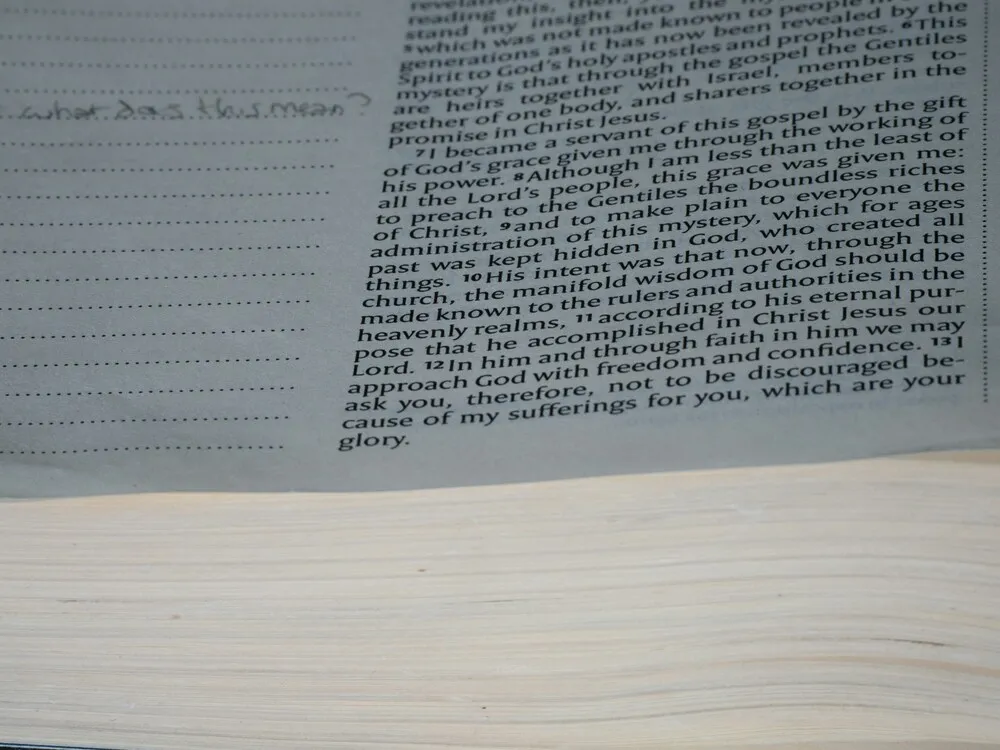
はじめに
社内での情報共有は、ビジネスを円滑に進める上で欠かせない行為です。しかし、「外部から入手した資料をコピーして会議で配布する」「購入した書籍の一部をスキャンして関係者にメールで送る」といった行為は、一見すると日常的な業務に見えますが、著作権法との関係で重大なリスクをはらんでいます。
「社内資料として著作物を関係者に配布するのは著作権法違反ですか?」という疑問は、多くの企業法務担当者が直面する問題です。特に法務部が存在しないスタートアップ企業などでは、各役職員が法律を意識する必要性が高いと言えるでしょう。
この記事では、提供された資料に基づき、社内資料の配布行為が著作権法にどのように抵触し得るのか、そして企業が取るべき対策について、詳しく解説します。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
結論(先に要点)
- 社内であっても、コピー・スキャン・PDF化・サーバ保存は原則として複製(21条)に当たり、許諾が必要。多数の従業員が閲覧できる状態に置けば、公衆送信・送信可能化(23条)が問題になり得る。
- 私的複製(30条)は個人・家庭等の範囲に限られ、業務目的の社内共有には通常適用されない。引用(32条)や情報解析(30条の4)の例外も、会議で“読ませる/理解させる”用途には広がらないと考えられる。
1. 近時裁判例:東京新聞(中日新聞) vs 首都圏新都市鉄道(つくばエクスプレス)

近年、裁判例において、社内イントラネットで新聞記事を共有した事案において、著作権侵害が認められました。
事案は、被告会社が2005〜2019年度にわたり、東京新聞等の記事をスキャン→社内イントラに掲載。全従業員(約530〜730人)が閲覧できる状態だった、というもので、一審(東京地裁 令和4年10月6日)は複製・公衆送信の侵害を認め192万3,000円を命じ、控訴審(知財高裁 令和5年6月8日)も侵害を肯定し、記事1本あたり5,000円で約133万円の賠償を命じた。最高裁は2024年4月、上告を退け確定しました。
新聞記事の無断使用で著作権を侵害されたとして、日本経済新聞社と中日新聞社がそれぞれ、つくばエクスプレスを運行する第三セクター、首都圏新都市鉄道(東京)に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、知財高裁は8日、いずれも同社による著作権侵害を認めた。
2. そもそも著作権とは何か?—無許諾利用が招くリスク
著作権法では、著作物を創作した著作者に対し、その創作活動の成果を守るための権利が与えられています。近年では、ウェブサービス等を通じて、他人の文章、画像、音楽、動画などの著作物を極めて簡単に利用できてしまうため、特に慎重な検討が必要です。
1-1. 「著作物」の定義と権利の束(支分権)
まず、著作権の保護対象となる「著作物」は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。ウェブサービスで利用対象となる他人の文章、画像、音楽、動画などは、基本的に著作物性が認められることが多いと考えられます。
著作者に発生する権利は、大きく分けて二つあります。
1. 著作者人格権: 著作者の人格的利益を保護するための権利(公表権、氏名表示権、同一性保持権)。著作者人格権は、著作者が精神的に傷つけられないための権利であり、譲渡することはできないとされています(59条)。
2. 著作権(著作財産権): 著作者の経済的利益を保護するための権利。
この著作権(著作財産権)は、複製権や公衆送信権など、利用態様に応じた様々な個々の権利の束であり、これらは「支分権」と呼ばれます。
1-2. 社内配布で問題となる主要な権利
社内資料として著作物を配布する行為が著作権侵害となるかどうかは、上記の「支分権」のうち、どの権利を侵害するかによって決まります。
1. 複製権(21条): 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に作成する権利です。
◦ 紙の資料をコピーする行為や、電子データをサーバーに保存する行為は「複製」に該当します。
2. 公衆送信権等(23条): 著作物をインターネット等により公衆(一般の人)に向けて送信することに関する権利をいいます。
◦ 電子ファイルをメールで社内関係者に送信したり、社内サーバーにアップロードして共有したりする行為は「公衆送信」に該当する可能性があります。
他人が無許諾で著作物を利用するあらゆる行為が著作権侵害となるわけではありませんが、上記の各支分権のいずれかを侵害する行為を行った場合に著作権侵害となります。
3. 社内利用は例外的に許されるか?—権利制限規定の検討
著作権者の許諾なく支分権を侵害する行為を行った場合は、原則として著作権侵害となります。しかし、著作権法は30条以下において、例外的に著作権侵害とならない場合(権利制限規定)を認めています。
社内利用がこの例外に該当するかどうかを検討します。
3-1. 私的使用のための複製(著作権法30条)
権利制限規定の一つに「私的使用を目的とするための複製」が挙げられています。私的使用のための複製は著作者の許諾がなくても許されています。
「私的使用」とは、一般的に個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内での使用を指します。企業内での利用は、たとえ配布先が限られていても、「事業活動の一環」として行われることが通常であるため、この「私的使用」の範囲を超える可能性が高いと考えられます。
したがって、社内資料としての配布や共有は、原則として私的使用の例外には該当しないと解釈されることになります。
3-2. その他の権利制限規定(企業活動との関連が深いもの)
企業活動やデジタル化に関連する権利制限規定(著作権者の許諾なく利用できる例外)には、主に以下のようなものがありますが、これらも社内配布行為を直接的に許容するものではありません。
| 権利制限規定 | 概要と社内配布への適用可能性 |
| 引用 (著作権法32条) | 公表された著作物を公正な慣行に合致し、正当な範囲内で利用する場合。主従関係(引用部分が主、被引用部分が従の関係)が必要であり、資料全体をコピーして配布する行為には適用されません。 |
| 機械学習 (著作権法30条の4) | AIの学習など、思想や感情を自ら享受したり他人に享受させたりすることを目的としない場合に利用可能とされています。社内会議資料として「読んで理解させる」ことが目的の場合、これは「享受目的」に該当し、適用外となります。 |
| 立法または行政の内部資料 (改正著作権法42条等) | 立法または行政の目的のために内部資料として必要な場合に、利用者間に限って公衆送信等ができるとされましたが、これは民間企業には適用されません。 |
結論として、社内資料として著作物(特に外部の著作物)をコピーして関係者に配布する行為は、原則として著作権者の複製権や公衆送信権を侵害する行為に当たる可能性が高く、許諾を得ずに実行することは法的なリスクを伴います。
4. 著作権侵害が発生した場合の法的責任と企業の対策
著作権侵害が発生した場合、企業は民事責任と刑事責任の両方を問われる可能性があります。
4-1. 民事責任:差止請求と損害賠償請求
著作権を侵害された著作権者は、以下の民事上の救済手段を求めることができます。
著作権侵害の賠償額に関する考察は、弊所記事「著作権侵害の警告が届いたらどうする?アクセス数がゼロでも損害賠償を払う必要があるの?」をぜひご参照ください!
4-2. 刑事責任:親告罪と罰則
著作権法は著作権侵害について罰則規定を有しており(119条)、著作権を侵害した者は、刑事責任も問われます。
ただし、著作権侵害の罪は、原則として被害者である著作権者等による告訴がなければ刑事責任を問われることのない親告罪です(123条)。
4-3. 著作権確保のための実務上の対策
著作権侵害のリスクを避けるためには、「著作権者に許諾を得る」または「契約で権利を確保する」ことが必須です。
(1)外部への委託時や権利譲渡を受ける際の注意点
社内で利用する資料やシステムを外部のデザイナーやエンジニアに作成してもらう場合、著作権を確実に会社に帰属させるための契約上の工夫が不可欠です。
1. 支分権の明記: 著作権を譲渡する際、単に「著作権を譲渡する」とだけ記載するのでは不完全です。61条2項により、27条の権利(翻訳権、翻案権)28条の権利(二次的著作物に対する原著作者の権利)明記していないと移転していないと推定されるためです。
2. 著作者人格権の不行使特約: 著作者人格権は譲渡できません。したがって、会社が著作物を自由に改変・利用できるようにするためには、「著作者人格権を行使しない」ことを契約で約束してもらう必要があります。
(2)社内規定の整備
社員が職務として創作した著作物(職務著作)については、一定の要件を満たす場合に、著作者は原則として法人その他の使用者であるとされています(15条)。
また、職務発明(特許権)の取り扱いと同様に、著作権についても、従業員に対して「職務上発生した知的財産権が会社に帰属する旨」や「在籍中および退職後の秘密保持義務」を内容とする誓約書の提出を求め、就業規則にもこれらの内容を規定しておくことが望ましいとされています。
5. まとめ――企業が取るべき対策チェックリスト
著作権侵害のリスクは、IPOの審査やM&Aのデューディリジェンス(DD)においても当然に審査される重要なポイントです。コンプライアンスを重視し、権利処理を明確にすることで、将来の紛争を未然に防ぎ、事業の健全な発展を目指しましょう。
- 「外部著作物の丸ごとPDF配布禁止」「引用ルールは遵守。主従関係・必然性・出所明示を厳守。」「会議配布は要約資料を原則」「イントラ掲載は部門限定・期間限定・必要なら包括許諾」「研修による知識アップデート」
- 外部記事は自社作成の要約で共有し、必要最小限の引用にとどめ出所を明示。元記事URLで正規に誘導。
- 新聞社・出版社・著作権管理団体との包括許諾契約を検討。部門限定・期間限定のイントラ掲示ルールを契約に落とし込む。
- DMS/イントラは最小権限・ビューア数の上限・掲載期限を設定。アクセス/配布ログを保持。
比喩的ですが、著作権は、まるで上流の水をコントロールするダムのような権利です。ダム(著作権者)が許可(ライセンス)を与えなければ、下流(利用者)は水を自由に使うことができません。もし無断でパイプ(コピーや公衆送信)を引いて水を流してしまうと、それは不法な取水(著作権侵害)となり、後からダムの管理者(著作権者)に止められたり、損害を賠償させられたりするリスクが発生します。
社内の資料配布も、この「不法な取水」にならないよう、必ず上流(著作権者)からの許可を得て、適正なパイプライン(契約やライセンス)を通じて行う必要があるのです。
昔からやっている、先輩が同じようなことをしていた、では済まされない問題になる可能性があるので、ご用心を!
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。