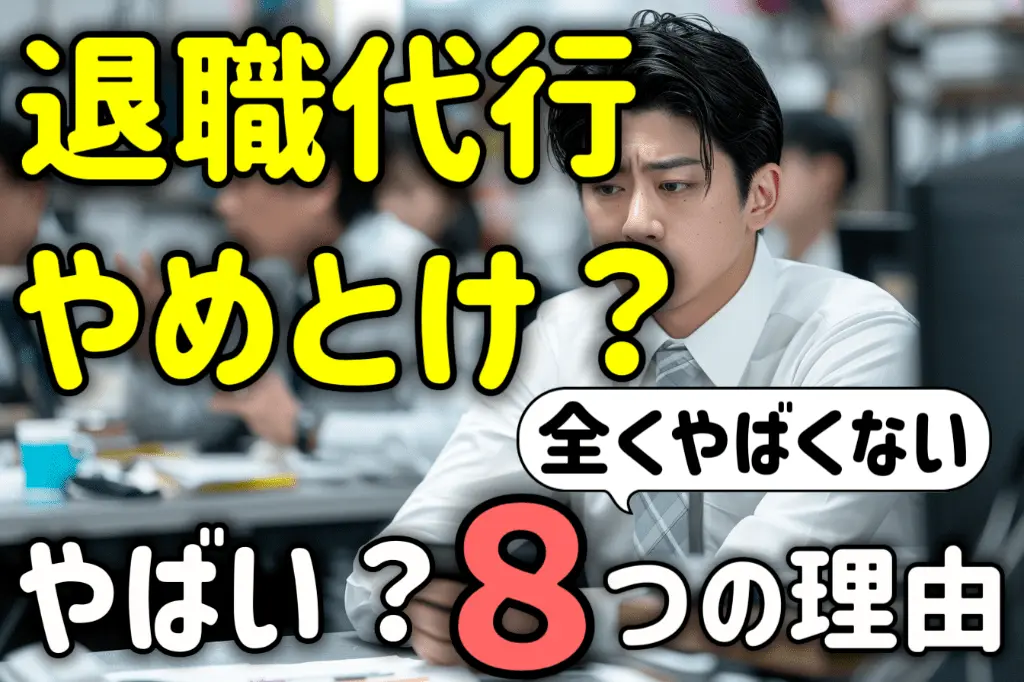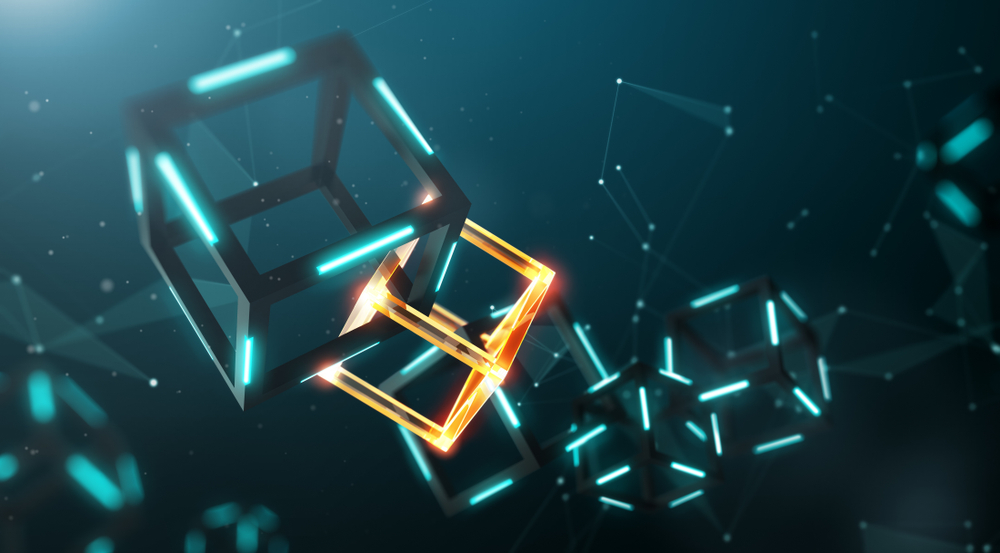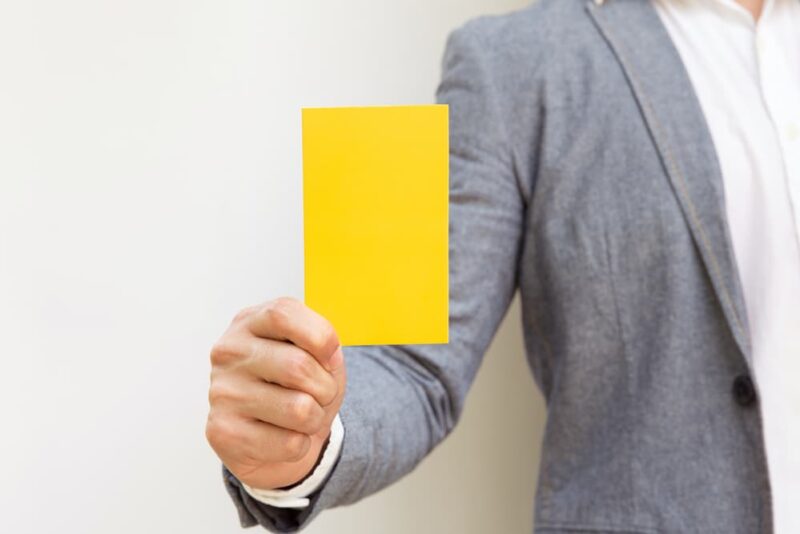ステルスマーケティングは何法に違反?景品表示法の要点と線引き【2025年版】

はじめに
近年、食べログ登録事業者などに見られる「ステルスマーケティング(ステマ)」が問題視されていますよね。
特にモデルやタレントといったインフルエンサーが、自身のブログやインスタグラムを通して企業の商品を宣伝するという手法については、その広告効果の高さからこぞって企業が取り組んでいます。
ですがこのようなPR(広告)手法は、いわゆる「ステマ」として、違法なんじゃないの?と不安に思う方もいるかと思います。
そこで今回は、「ステマ」とは何か、何が問題なのか、法律に違反するのか、違反しないためにはどうすればよいのかなどについて、分かりやすく具体的に解説していきたいと思います。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
【ざっくりまとめ】
「インフルエンサーに商品を渡して感想を投稿してもらった。#PRは要る?」——結論、広告であるのに広告と分からせない表示は、2023年10月1日以降、景品表示法の不当表示として違法です。消費者庁は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示」を指定し、広告である旨の明示(例:広告/PR/提供等のわかる表示)を求めています。違反の主な処分対象は広告主(事業者)で、原則として投稿者本人ではありませんが、共同提供等では投稿者も対象になり得ます。措置命令の実例も出ています。
1 ステマとは

「ステマ」とは、ステルスマーケティングの略で、消費者に対し、広告だということを隠しながら行う広告のことをいいます。
【注:広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」は、「一般消費者が事業者の表示であると認識できない表示」として不当表示に該当するとされています(景品表示法5条3号)。】
いわゆる「やらせ」や「サクラ」です。
例えば、ブロガーがある商品についてその使用感や、「おススメです☆」といった内容の記事をアップしたとします。
この記事を読む限りでは、あたかもそのブロガーが愛用している商品を紹介しているように見えるのに、実は愛用品でもなんでもなく、ただ企業から頼まれて記事を書いているのであれば、それは「ステマ」にあたります。
よくあるステマのパターンとしては、以下の2種類があります。
- なりすまし型
- 利益提供型
順番に確認しましょう。
(1)なりすまし型
「なりすまし型」とは、業者が一般消費者になりすまして口コミや評価を書くタイプのものです。
有名なものとしては、業者が利用者になりすまして特定の飲食店に好意的な書き込みをしていた「食べログ事件」があります。
好意的なものだけではなく、利用者のフリをしてライバル企業に対し悪口を書き込む行為もこのタイプにあてはまります。
(2)利益提供型
「利益提供型」とは芸能人など社会的な影響力のある人(インフルエンサー)に報酬を渡して宣伝を依頼するタイプのものをいいます。
例えば、先ほど解説したように、業者から報酬を受け取ったうえで、宣伝であるのにそれを隠してあたかも愛用しているかのような投稿をする場合です。
このタイプのステマは、ブログやFacebook、YouTubeなどのSNSを通して行われる傾向があります。
なお、「ステマ」にあてはまるかどうかに報酬の有無は関係ありません。
たとえ無報酬で宣伝を行っていたとしても、「宣伝であることを隠して行われた宣伝行為」」であるならばそれは「ステマ」になります。
このような形で行われるステマですが、一般的に「悪いこと」というイメージを持たれていますよね。
では、具体的にステマの何が問題なのでしょうか?次の項目で解説します。
2 ステマの何が問題なのか?

(1)消費者を騙していること
ステマの問題点を一言でいえば、「消費者に誤った印象を与えて正しい判断をできなくさせている点」です。
私たちが商品やサービスを選ぼうとしたとき、口コミやレビューなど、中立的な第三者の意見をある程度の信頼性をもって参考にします。私たちは商品やサービスについて完璧な知識を持っていないからです。
口コミは普通、実際に商品を使った人が書き込みものであるため、これを参考にする分には何ら問題はありません。
これに対して、自分が信頼した口コミが実は広告(宣伝)だったらどうでしょうか。
広告は普通、その商品やサービスについて悪いことは書きません。消費者もそれは分かっているため、あらかじめそれが広告であると分かっていればそれなりのスタンスでその広告を見ます。
ですが、ステマのように、広告であることを隠してあたかも普通の口コミであるかのような表示をしたら、消費者は、広告よりも信頼性の高い情報としてこれを受けとります。
その結果、普通であれば広告に払うであろう注意を払うことができず、商品に対して正しい判断ができなくなります。
このように、消費者を騙し、誤った印象を与えることがステマの問題点なのです。
(2)業界全体に対する信用力が低下すること
ステマの二つ目の問題点は、違法なことをした一事業者のみならず、同じ(もしくは近接する)業界全体への不信感を醸成してしまうことです。
実際、過去に起きた「食べログ事件」「ぺ二オク事件」では、ステマをした一事業者だけでなく、ただでさえ「虚業」といわれるIT業界や、関連する著名人全体の信用が下がる結果となりました。こうなると、不買活動などが生じかねないため、業界全体として経済的な不利益となるわけです。
(3)炎上のリスクがあること
ステマの3つ目の問題点として、消費者を騙すような広告手法という点から、ネット民やその他の消費者から大々的な非難をうけることが考えられます。これをきっかけにインターネット上でいわゆる「炎上」をしてしまう可能性があります。
また、ステマがバレて炎上したことで信用を失った結果、常に「これもステマなんじゃないか」という疑いを持たれる可能性があります。
そうすると、正当なことをしてもそれを純粋に評価してもらうことが難しくなり、今後の企業活動に深刻な影響を及ぼすことになってしまいます。
ステマには以上の問題点があるため、次の項目で説明するとおり、法律上も、「景表法(けいひょうほう)」という法律によって規制されます。
3 ステマに対する法律規制

「景表法」とは、企業が商品やサービスを宣伝・広告するときのルールを定めた法律です。
商品やサービスについて、ウソの表現や大げさな表現をされたら、私たちはその商品の本当の価値を判断できなくなりますよね。
私たちが間違った判断をしないよう、宣伝する側を縛るルールが「景表法」なのです。
景表法では宣伝・広告の方法として「不等な表示」を禁止していて、その内容として次の2つがあります(景品表示法5条1号・2号)。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
「優良誤認表示」とは、商品やサービスの内容について、実際の物よりも著しく良く見せかけたり、他社の競合サービスよりも著しく良く見せかけるような場合をいいます。
要するに、大して良くもない商品(普通の商品)を「これはとっても素晴らしい商品なんですよ!」と紹介して、その質を偽ることをいいます。
「有利誤認表示」とは、商品やサービスの値段などを著しく有利にみせかけることをいいます。
消費者に「これってとってもお得なんじゃ・・・!」と思わせておきながら、実際には全然お得じゃないような場合が有利誤認表示にあたります。
これら2つにあてはまる宣伝方法については、景表法で禁止されています。
ステマの場合には、商品の「価格」を偽るというよりも、本来は広告であるのに、それを秘匿して、「この商品ってこんなに素晴らしいんですよ!」という形でPRする手法ですから、「内容を偽る」という意味で「優良誤認表示」規制に違反し、景表法に違反する可能性があります。
【注:なお、景品表示法の「表示」には、口頭による広告その他の表示も含まれます(景品表示法2条4項)。】
(景表法について詳しく知りたい方は、「盛りすぎ広告に注意!5分でわかる景表法に違反しないためのポイント」をご覧ください。)
4 ステマはどのような場合に景表法違反となるのか

(1)景表法違反の要件
では、どのような場合にステマが景表法違反となるのでしょうか?
景表法違反になる広告とは、問題となる広告が、
が必要です。
①不当な「表示」にあたるか?
まず、景表法が禁止している不当な「表示」とは、事業者が、集客のための手段として商品やサービスについて行う宣伝・広告に関するものをいいます。
ステマで行われている、「事業者がユーザーを装って口コミを投稿したり、ブロガーに報酬を支払って自社の商品を紹介してもらう行為」などは、まさしく集客のために行う商品・サービスについての宣伝なので、景表法上の「表示」にあてはまります。
そして、これらの行為は商品の「内容」についてのものなので、次に、不当表示のうち「優良誤認表示」として規制をうけるかどうかを検討することになります。
②優良誤認表示にあたるか?
景表法上の「優良誤認表示」として認められるためには、商品やサービスについての内容を実際の物よりも「著しく」良く見せかけている必要があります。
セールストークの範囲を超えて、「著しい」お得感を演出している場合にのみ、優良誤認表示にあたり違法となります。
ステマについていえば、事業者が集客のために自ら、または第三者に頼んで商品やサービスの口コミ情報を掲載させたときに、「商品・サービスの中身について、実際のものまたは競合他社のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤解されるような内容」であった場合にのみ、景表法上の「優良誤認表示」にあたり、違法となります。
要するに、常識的に考えてそのステマが「度を越えている」「さすがにそれはやりすぎでしょ」といったエゲつないケースについてのみ景表法違反となります。多少大げさに宣伝したくらいでは、ステマは違法にはなりません。「社会一般で許される限度を超えた場合」に初めて「著しく」欺瞞的(ぎまんてき)な広告であるとして、そのステマは違法になります。
③一般消費者が事業者の表示であると認識できない表示
これは、まさに広告であるのに、広告とは分からない表示をする場合が該当します。
この点については改正法の内容を項を改めて説明します。
5 ステマはどのような場合に景表法違反となるのか
(1)規制の概要
運用基準が前提としているのは、次のような消費者の行動パターンです。
- 消費者は、「事業者による広告だ」と分かっていれば、
→ ある程度の誇張・宣伝表現が含まれている前提で判断する。 - 一方で、「第三者の中立な口コミ・感想」だと思ってしまうと、
→ その情報をより信用してしまう。
にもかかわらず、実際には事業者が内容に関与しているのに、それを隠して第三者の口コミのように見せると、消費者の自主的・合理的な選択が阻害される——これがステマ規制の発想です。
(2)ステマ規制の段階
ステマ規制の判断は、大きく二段階です。
- その投稿・表示は「事業者の表示」(=広告等)か?
- 事業者の表示だとすれば、それであることが一般消費者にとって明瞭か?
①従業員・グループ会社による投稿
- 商品の販売を担当する社員や役員が、自身のSNSで自社商品の写真やテキストを投稿し、販促を図るケース
- 「一般人のレビュー」に見せながら、実は商品企画チームのメンバーが運営するアカウント…など
②インフルエンサー・レビュアー等への依頼
- 事業者がインフルエンサーに対し、「この商品の良さを書いてほしい」など、投稿内容を指示している
- ECサイトのレビューを集めるために、ブローカーや購入者に依頼し、特定の内容でレビュー投稿させる
- 報酬を約束していなくても、「投稿すれば今後も商品提供・取引が期待できる」ことを匂わせ、事業者の意向に沿った投稿をさせる
③アフィリエイト広告
- 広告主がアフィリエイターに委託し、アフィリエイトサイトやブログ上で自社商品を紹介させるケース
このような場合、投稿者が個人であっても、実質的に事業者の広告と評価されることがあります。
(3)「事業者の表示」にあたらない主なパターン
逆に、次のようなケースは、通常は「事業者の表示」にはなりません。
- 一般ユーザーが、自分の好き嫌いに基づき、自主的に商品レビューや感想を投稿している
- メディア企業が自主的な編集判断で記事・番組を制作している(通常の取材・書評・番組放送など)
- 事業者と投稿者の間で、表示内容について具体的なやり取りが一切なく、単なる試供品配布の結果として口コミが生じているだけ…など
重要なのは、「事業者がその表示内容の決定にどこまで関与しているか」という実態です。
(4)「広告であること」が分かりにくいか?
次に、「事業者の表示」だと判断される場合に、その投稿が「一般消費者にとって、事業者による広告だと明瞭か?」が問題になります。ここで、「広告明示」のあり方が問われます。
①NGとなりうる例(広告であることが不明瞭)
運用基準は、「事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載されている」例として、例えば次のようなケースを挙げています。
- そもそも広告である旨の記載が一切ない
- 冒頭に「広告」と書いているのに、本文中で「第三者として感想を書いています」と書き、どちらか分からなくしている
- 動画の冒頭に一瞬だけ「PR」と表示するが、視聴者が認識できないくらい短い表示
- 長い動画で、途中や最後だけに「PR」と出し、視聴者が見落としやすい
- 「広告」である旨を、小さなフォントや薄い色で、ページのいちばん下に表示するだけ
- SNS投稿で、大量のハッシュタグに紛れ込ませて「#PR」と書き、他のタグと区別がつかない
このように、広告であることを形式的には書いていても、「実質的に分からない」状態ならアウトになり得る点に注意が必要です。
②OKとされる広告明示の基本形
一方、運用基準やQ&Aは、「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭」と評価される例として、次のような表示方法を挙げています。
- 「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」などの文言を明示する
- 「A社から商品の提供を受けて投稿しています」「B社から依頼を受けた有償広告です」等と、文章で明確に説明する
このとき重要なのは、単に文言を入れればよいのではなく、以下のような2つの原則です。
- 明瞭性
- 表示内容が、広告であることを明確に伝えていること
- 曖昧な表現(「一部PRを含みます」など)に頼りすぎない
- 認識の容易性
- 消費者が容易に認識できる位置・大きさ・表示態様になっていること
- 冒頭付近に、他の文字と同程度以上の大きさ・コントラストで示す
- 長尺動画や複数ページの場合は、視聴・閲覧の途中でも分かるように適宜表示する
(5)「広告明示」が要らないケースは?「広告であること」が分かりにくいか?
規制は、「事業者の表示であることが明らかなもの」までも制限する趣旨ではありません。
例えば、次のようなものは、通常、広告であることが社会通念上明白とされます。
- テレビ番組とは区切られた「テレビCM」
- 新聞紙面の広告欄(「広告」と枠表示されたもの)
- 商品紹介が主目的の雑誌特集など
- 事業者自身の公式ウェブサイトや公式SNSアカウント上の表示
もっとも、自社サイトや自社SNSであっても、あたかも第三者の客観的意見であるかのように見せかける場合には注意が必要です。
例えば次のようなケースでは、第三者コメント部分についても「事業者の表示である」ことをきちんと明示する必要があります。
- 事業者が専門家に依頼してコメントをもらい、自社の方針に沿うように編集して掲載しているのに、
→ あたかもその専門家が自主的に書いているかのように見せている
→「弊社から○○先生に依頼し、いただいたコメントを編集して掲載しています」等と明示するのが望ましい
なお、規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります(消費者庁)
6 類型ごとの違反事例
とはいえ、これだけでは抽象的です。
ステマには、冒頭で説明したとおり、
- なりすまし型
- 利益提供型
の2種類があるので、その類型ごとに具体的にどのような場合にステマが違法となるのかを、次の項目から確認していきましょう。
(1)なりすまし型
-
- 【事例①】
- 成績不振のある飲食店を経営する事業者が、飲食店の口コミサイトやSNS等で、利用者になりすまして口コミを投稿し、「このお店は宮崎の地鶏を使っていてとても美味しかった!オススメです!」などと書き込み、実際には宮崎の地鶏を使用していないのにあたかも使用しているかのように消費者に勘違いさせた事例。
この事例では、ユーザーが実際にその飲食店の食事をしたわけではないのに、あたかも食事をしたかのように記載し、なおかつ、食材の点について「地鶏を使っている」などとウソの表現(口コミ)を記載しています。これは、ユーザーを装い、なおかつ、真実は使用していない食材が使用されているかのように、積極的に虚偽の情報を提供しているため、「著しく優良であると誤解させるような内容」といえ、違法になります。
-
- 【事例②】
- 商品を販売する事業者が口コミ代行事業者に報酬を払って依頼し、自分の販売する商品に関する口コミサイトに口コミをたくさん書かせて無理やり評価を上げ、もともとは低評価だったのにあたかも利用者から高評価を得ているような印象を与えた事例。
実際の事業者のサービスの内容・質やホスピタリティに関係なく、金にものを言わせて、意図的に評価をつり上げています。しかも、もともとこの会社は「低評価」であったのに、それを「高評価」にしている点からすると、このステマは「やりすぎ」であって、「自社の商品が競合他社のものよりも著しく優良であると誤解させるような内容」「一般消費者が事業者の表示と認識できない表示」といえ、違法になりえます。
(2)利益提供型
-
- 【事例③】
- 事業者が、ブロガーに対し報酬を支払って商品の宣伝を依頼し、そのブロガーが、十分な根拠もないのに「〇〇ゲットしました!シミやそばかすを予防して美白に効果的です!オススメ☆」などと投稿した事例。
十分な根拠もないのに、あたかも効果があるかのような投稿をさせていること、また、ブロガーに報酬を支払っている(その意味で、ブロガーの記載は広告となる)にもかかわらず、報酬の支払いについて記載がありません。このような手法は、商品について「著しく優良であると誤解させるような内容」といえ、違法となります。
なお、優良誤認表示が疑われる場合、消費者庁長官は合理的根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出がないときは不当表示とみなされ得ることになります(景品表示法7条2項)。
-
- 【事例④】
- 事業者が出版社に報酬を支払って、自社の商品について「他社の〇〇よりも▲▲でとても優秀!」などというウソの内容の記事を書かせた事例。
具体的に、ウソも織り交ぜて記事にしているため、商品の中身について、実際のもの・他社のものよりも「著しく優良であると誤解させるような内容」といえ、違法になります。
景品表示法は一切の比較広告を禁じているわけではありませんが、客観的実証等がない比較で消費者を誤認させる場合は不当表示となり得ます。
-
- 【事例⑤】
- テレビ番組、配信動画や雑誌などの記事の中で、俳優に「体験談形式」で、商品の良さを語ってもらう事例。
この事例では、媒体の中に「広告」であるとの表示がないことから、それを見た消費者は中立的な意見と誤解し、「この商品は俳優の◯◯さんが気に入って使ってるからいい物なんだ!」と勘違いする可能性が高いです。その意味で、このような広告手法は、「著しく商品の品質などをよく見せるもの」「事業者の表示であると認識できない表示」として違法になります。
-
-
- 【事例⑥】
-
テレビドラマのワンシーンで、俳優に自社商品を何気なく使っているシーンを盛り込んで放映してもらう事例。
これは、「プロダクト・プレイスメント」(略称:PP)という広告手法で、広告であると消費者に気付かせずに訴求するものです。
PPについては、作中で俳優などが積極的に商品を推奨するようなものでない限りは、消費者に与える影響もわずかなので、そもそも「表示」とすらいえない場合もあります。ただし、景品表示法の「表示」は口頭その他の表現も含むため(景品表示法2条4項)、PPであっても個別事案の態様によっては「事業者の表示」に該当する可能性があります。
-
- 【事例⑦】
- 事例⑤と同じように、テレビ番組などの中で,俳優などが商品の使い心地を賞賛する体験談を述べてもらう形式にしたものの,報酬をもらって推奨表示をしていることを視聴者が簡単にわかるような表示をしている事例。
この場合、俳優を起用した通常のテレビCMと同じように、俳優に報酬は支払っていることが消費者からみてわかる、広告であることが明瞭に認識できる表示がある場合、当該点を理由とする「事業者の表示と認識できない表示」には該当しないという整理となります。
7 商品をPRする上で気をつけること

以上の事例を踏まえると、事業者が商品やサービスをPR(広告)する場合には、以下の点に気を付けるべきといえます。
- その表示が「広告」であるということを消費者がわかるようにきちんと明示すること
- 根拠のない表示やウソの表示をしないこと
8 ステマが景表法に違反した場合のペナルティ

さて、ステマが景表法に違反した場合には、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
ステマをした事業者に対して、以下の3種類のペナルティが発動される可能性があります。
- 民事上のペナルティ
- 行政上のペナルティ
- 刑事上のペナルティ
(1)民事上のペナルティ
ステマが景表法に違反して違法となる場合、ステマに騙されて商品を買ったりサービスを利用した人たちから、それによって生じた損害の賠償請求をされる可能性があります。
(2)行政上のペナルティ
景表法に違反した場合、民事上のペナルティのほか、「消費者庁」という行政からのペナルティを受けます。
ペナルティ発動までの流れとしては、景表法違反があった(との疑いがある)からといって、いきなり制裁が下されるわけではありません。
事業者には、まず最初に、①「言い訳」のチャンス(これを「弁明の機会」といいます。)が与えられます。
弁明の機会において、うまく言い訳に成功すれば、無罪放免で、何もペナルティはありません。他方で、言い訳に失敗し、消費者庁から景表法違反だと認定されてしまったら、②「措置命令」(改善を促す命令のこと。)が出されます。
「すいませんでした!」といって平身低頭平謝りをして、この措置命令にきちんと従えば、それ以上のペナルティは、基本的にはありません。
他方で、措置命令に従わないということになると、次の項目で説明する「刑事上のペナルティ(罰則)」が発動されてしまいます。

なお、「優良誤認」表示or「有利誤認」表示にあたる行為が認定されたケースでは、「課徴金」といって、違法な広告によって儲けた売上の一部からキャッシュを没収する制裁処分がくだされることもあります(景品表示法8条)。
没収される課徴金の額としては、
- 課徴金の額:対象商品・役務の売上額の3%
- 対象期間:3年間
で算出した額です。例えば、違法なステマの対象商品の年間売上が10億円のケースでは、最大で9000万円(10億×0.03×3年)ものキャッシュが国に持っていかれてしまいます。
【注:不当表示を中止して5年以上経過、相当の注意をした等の場合は課徴金の全部・一部が免除される。根拠条文:景品表示法12条7項、8条ただし書】
なお、事業者が違反行為を自主申告した場合や、被害者への自主返金をした場合には、刑事事件における「自首」と同じように、温情で課徴金を特別に減額する「リーニエンシー」という手続きも用意されています(景品表示法9条)。
(3)刑事上のペナルティ
さらに、上で解説した措置命令に従わない場合には、
- 最大2年の拘禁刑
- 最大300万円の罰金
のいずれか、または両方が科される可能性があります(景品表示法46条)。
以上が「ステマと景表法」の問題になりますが、ステマをする際には、実は、景表法以外にも他の法律規制があるため、これらの規制をクリアする形で広告をする必要があります。
次の項目で確認していきましょう。
9 ステマの他の問題点・法律規制

やりすぎのステマ行為に対しては、景表法とは別に、以下の罰則が科されてしまう可能性があります。
- 信用棄損罪
- 偽計業務妨害罪
順番に確認しましょう。
(1)信用棄損罪
「信用棄損罪」とは、人や会社の経済的信用力に対する評価を傷つける犯罪行為です。
「なりすまし型」のステマの場合、利用者になりすまして自社に好意的な評価の口コミを投稿するケースと、ライバル会社について根拠のない「でっち上げの悪口」を投稿するケースがあります。
ライバル会社についてウソの「でっち上げ口コミ」を投稿した結果、ライバル会社やその商品に関する社会的評価が下がってしまった場合には、この「信用棄損罪」にあたる可能性があります。
信用棄損罪にあたる場合、ステマをした事業者に対しては、
- 最大3年の拘禁刑
- 最大50万円の罰金
のいずれかが科される可能性があります(刑法233条前段)。
(2)偽計業務妨害
「偽計業務妨害罪」とは、誰かを騙したり、ウソの情報を流すことで本来の業務を妨害する犯罪行為をいいます。
「でっちあげ口コミ」が原因でライバル会社の売上が落ちたり、営業を妨げてしまった場合には、この「偽計業務妨害罪」にあたる可能性があります。
問題の広告が、偽計業務妨害罪にあたる場合、ステマをした事業者に対しては、信用棄損罪と同じように、
- 最大3年の拘禁刑
- 最大50万円の罰金
のいずれかが科される可能性があります(刑法233条後段)。
10 小括

商品やサービスを提供する事業者にとって必要な「広告・宣伝」ですが、そのやり方によっては会社の信用を落としたり、違法な行為となってしまう可能性があります。
ステマについても同様で、効果的なマーケ手法なのですが、やり方を間違えれば違法な行為として様々なペナルティがあります。
しかも、ステマは、法律上のペナルティもさることながら、失敗にした場合には社会的な信用が大幅に低下するという制裁ももれなくついてきます。
事業者としては、こういったステマの問題や法律規制をきちんと理解したうえで、上手にPR(広告)するようにしましょう。
11 まとめ
これまでの解説をまとめると以下のとおりです。
- 「ステマ」とは、「ステルスマーケティング」の略で、消費者に対し、広告だということを隠しながら行う広告のことをいう
- ステマは「一般消費者が事業者の表示であると認識できない表示」にあたる可能性がある(景品表示法5条3号)
- ステマの種類としては①なりすまし型と②利益提供型の2種類がある
- ステマの最大の問題点は、消費者に誤った印象を与えて正しい判断をできなくさせる点
- 事業者が商品をPRするときには、その表示が「広告」であるということを消費者がわかるようにきちんと明示することと、根拠のない表示やウソの表示をしないことなどに気を付ける
- 景表法以外にも、ステマは信用棄損罪、偽計業務妨害罪にあたる可能性もあるので注意
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。