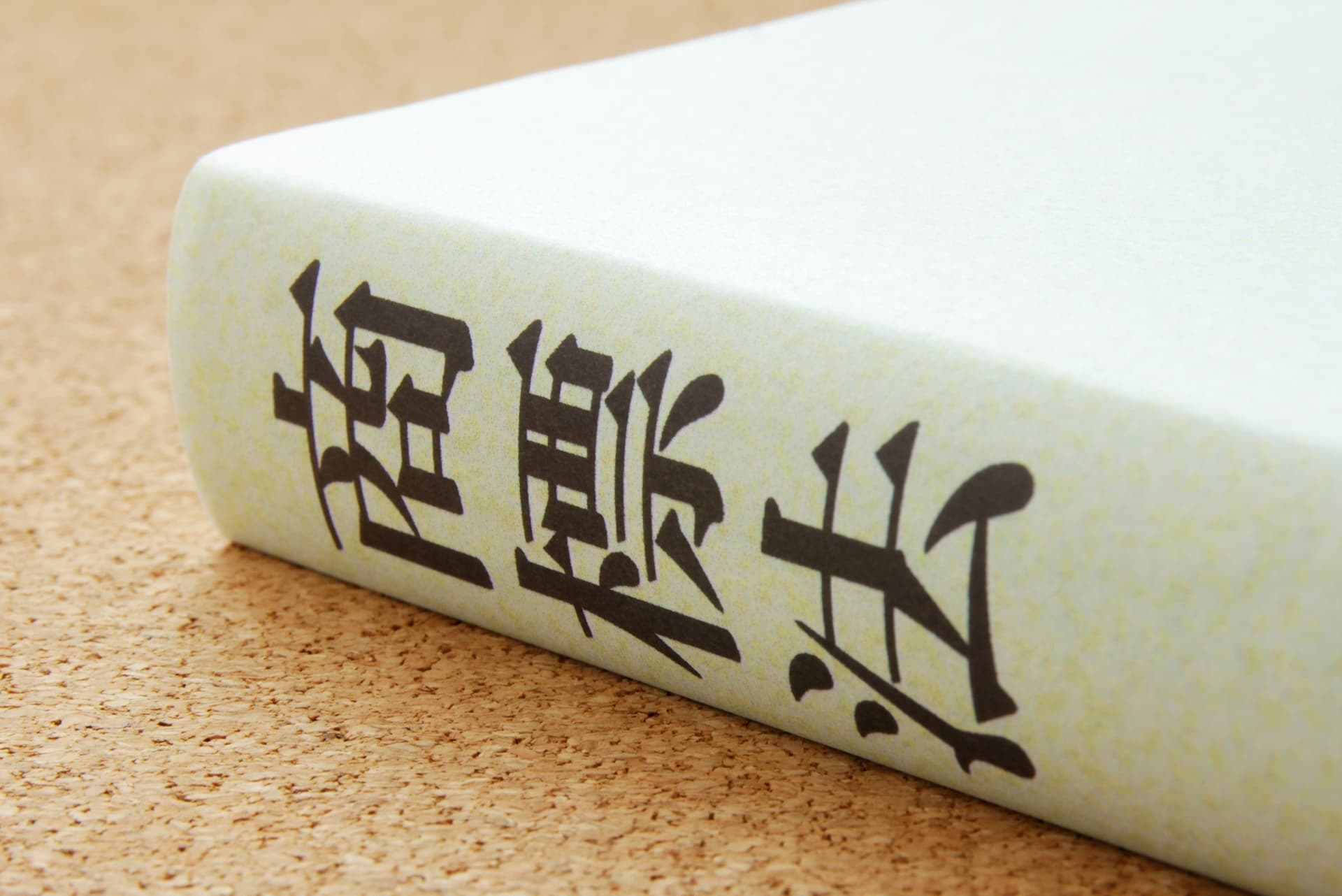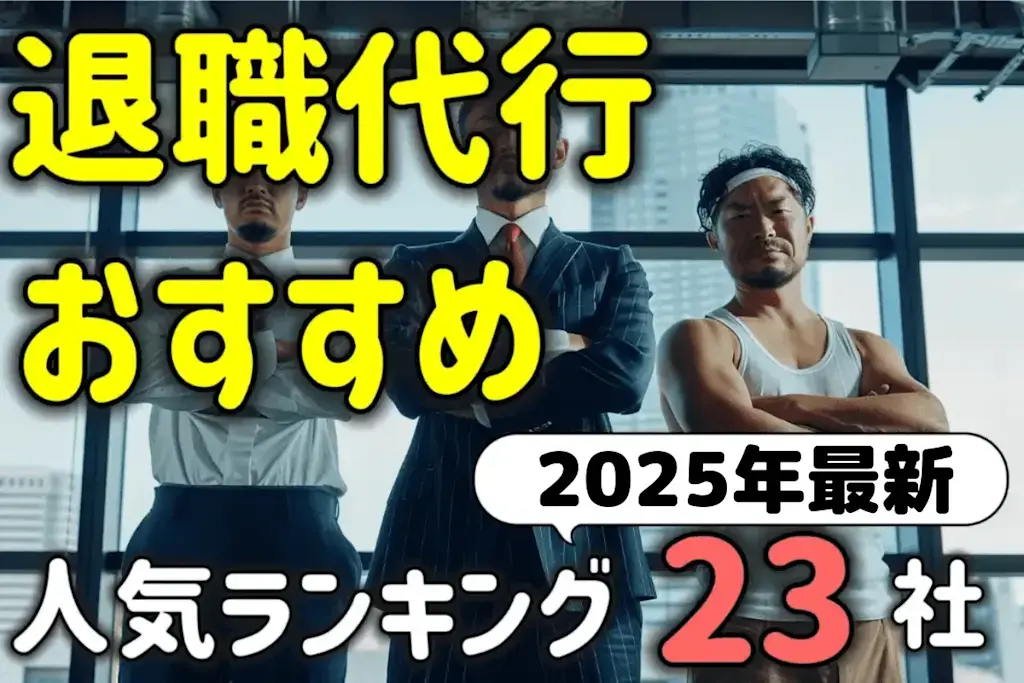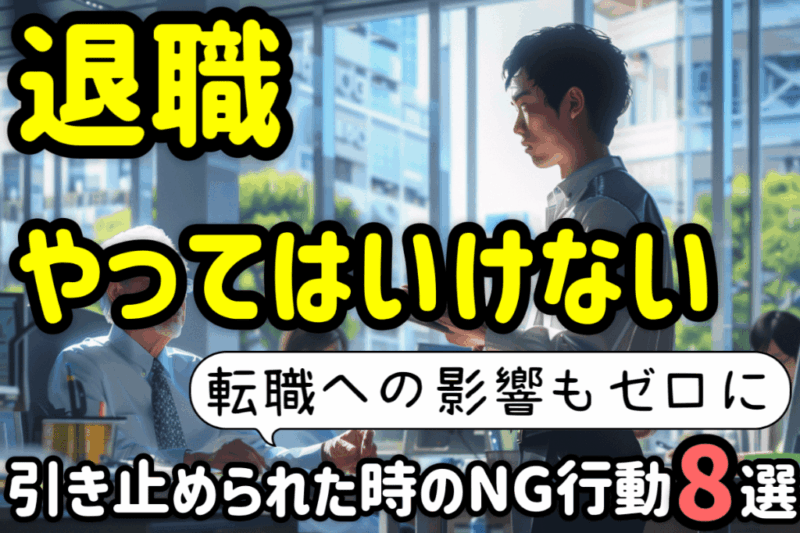オンラインゲームへの規制って?資金決済法など関連法律4つを解説!

はじめに
利用登録すれば、誰でも簡単にプレイできる「オンラインゲーム」。 課金要素なども設けやすく、新たに事業を行う人にとっては、収益を比較的上げやすいビジネスかもしれませんね。 しかし、オンラインゲームには、様々な法律規制が絡んでいることをご存じでしょうか。 この記事では、オンラインゲームを事業として行う場合、注意しておきたい4つの法律について、解説していきます。
1 オンラインゲームとは
 まず、オンラインゲームがどのようなものなのか、簡単に確認しておきましょう。 「オンラインゲーム」とは、インターネットにつながったPCやテレビなどの端末を使ってプレイするゲームのことです。インターネットゲームやネットゲーム、ネトゲなどとも呼ばれます。 複数人で協力・競争するタイプやプレイ結果によるランキングが表示されるタイプなど、様々なタイプ・ジャンルのオンラインゲームが存在しています。 このオンラインゲームを事業として行う場合、特に以下の2つの法律に注意が必要です。
まず、オンラインゲームがどのようなものなのか、簡単に確認しておきましょう。 「オンラインゲーム」とは、インターネットにつながったPCやテレビなどの端末を使ってプレイするゲームのことです。インターネットゲームやネットゲーム、ネトゲなどとも呼ばれます。 複数人で協力・競争するタイプやプレイ結果によるランキングが表示されるタイプなど、様々なタイプ・ジャンルのオンラインゲームが存在しています。 このオンラインゲームを事業として行う場合、特に以下の2つの法律に注意が必要です。
- 資金決済法
- 景品表示法
それぞれ、オンラインゲームのどのような要素に対して規制を行っているのか、解説していきます。
2 資金決済法=課金を規制
 オンラインゲームには、ゲームアイテム購入などの課金要素が含まれています。 この課金に関して規制を行っている法律が「資金決済法」です。
オンラインゲームには、ゲームアイテム購入などの課金要素が含まれています。 この課金に関して規制を行っている法律が「資金決済法」です。
(1)資金決済法とは
「資金決済法」とは、暗号資産(仮想通貨)や決済、銀行以外が行う為替取引などに対してルールを設けている法律のことです。 具体的には、以下の4つに関して、規制を行っています。
- 暗号資産(仮想通貨)(資金決済法63条の2以下)
- 前払式支払手段
- 資金移動
- 資金清算
オンラインゲームに課金を設ける場合、特に「前払式支払手段」について理解しておく必要があります。詳しく見ていきましょう。
(2)ゲーム内ポイント=前払式支払手段
「前払式支払手段」とは、「商品を手に入れるために、あらかじめお金を交換しておいたポイントやコインなど」のことをいいます。 具体的には、以下の定義に当てはまるものが「前払式支払手段」です。
- 金額または物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、または電磁的な方法で記録されていること
- 証票等に記載され、または電磁的な方法で記録されている金額または物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること
- 金額または物品・サービスの数量が記載され、または電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること
- 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること
(参考:一般社団法人日本資金決済業協会 前払式支払手段発行業の概要 前払式支払手段とは) 例えば、交通系電子マネー「Suica」や商品券などのように、あらかじめ対価を支払うことによって購入し、金額などが記録されているものが「前払式支払手段」に該当します。 ゲーム内ポイントもこの定義に該当するため、前払式支払手段の規制を受けることになります。
(3)前払式支払手段発行者の義務
前払式支払手段を発行している事業者には、主に2つの義務が発生します。
- 情報の提供義務
- 発行保証金の供託義務
①情報の提供義務
「情報の提供義務」は、Webサイトや商品券の裏などに、前払式支払手段の発行者として、その氏名や住所、苦情相談窓口の連絡先などの情報を掲載することを義務付けたものです。 具体的には、以下のような情報を提供する必要があります。
- 発行者の氏名、商号または名称
- 支払可能金額等
- 有効期限等がある場合は、その期限等
- 利用者からの苦情相談窓口の所在地および連絡先
- 利用することができる施設または場所の範囲
- 利用上の必要な注意
- 電磁的方法により金額等を記録している場合は、未使用残高またはその確認方法
- 約款等がある場合には、その約款等があること
(参考:一般社団法人日本資金決済業協会 前払式支払手段発行業の概要 主な規制内容) 事業者が情報の提供義務を怠った場合、最大30万円の罰金を科せられる可能性があります。
②発行保証金(供託金)の供託義務
「発行保証金の供託義務」は、前払式支払手段の未使用残高が毎年3月末か9月末時点で1,000万円を超えていた場合に発生する、お金の保全義務のことです。 具体的には、未使用残高の半額(最低500万円)を最寄りの供託所(法務局など)に預ける必要があります。 ここでいう「未使用残高」とは、前払式支払手段に変換後、まだ利用されていないお金のことです。 たとえば、100ポイント=1000円という価格設定でゲーム内ポイントを発行している場合、3月末か9月末の時点で未使用残高が100万ポイント(1,000万円分)利用されずに残っていると、供託義務が発生することになります。 それでは、何故お金を預けなくてはならないのでしょうか。 「発行保証金」とは、倒産やサービス終了などで、変換済の前払式支払手段が利用できなくなった場合に備えて預けるお金です。 もしも、そのような事態に陥ったときは、供託所に預けている発行保証金から、消費者に対して返金が行われます。 もしも、発行保証金の供託義務に違反してしまうと、
- 最大6ヶ月の懲役
- 最大50万円の罰金
のいずれか、または両方を科されてしまう可能性があります。 とはいえ、最低でも500万円を供託するとなると、スタートアップなどにとってはかなり厳しい義務といえます。 この義務を回避する方法はないのでしょうか。
3 発行保証金の供託義務を回避する方法
 供託義務を回避する方法としては、主に以下の2つが考えられます。
供託義務を回避する方法としては、主に以下の2つが考えられます。
- 有効期限を設ける
- ポイント消費を促すイベントを開催する
(1)有効期限を設ける
最も効果的な方法が、「有効期限の設定」です。 実は、有効期限が6ヶ月以内の前払式支払手段であれば、供託義務は発生しません。 有効期限を設けるときは、利用規約に以下のような表記をする方法が考えられます。 オンラインゲーム内で発行する「〇〇」(名称)の有効期限は、発行から180日とする また、利用者に対しても、いつ何ポイントの期限が切れるのか、わかるように表示しましょう。 そうすることで、利用者が期限切れ前にポイントを消費する可能性が高くなり、積極的にゲームをプレイする、さらなる課金を行う、などの効果も期待できます。
(2)ポイント消費を促すイベントを開催する
これは確実な方法ではありませんが、ポイント消費を促すイベントを開催することもひとつの手です。もしも、何らかの理由で有効期限を設けることが難しい場合は、この方法を取ってみることになります。 供託義務が発生するか否かを判断される3月末か9月末(基準日)の前に、未使用残高が1,000万円を下回るよう、イベントを開催してみましょう。 ただし、この方法を取るときは、有料ポイントと無料ポイントを分けて管理しておく必要があります。 実は、有料ポイントと無料ポイントを分けずに管理していた場合、その全額が「未使用残高」として換算されてしまいます。 本来であれば、発行保証金を支払わなくてもよいケースであっても、無料ポイント分が上乗せされ、支払わざるを得なくなってしまうこともあるのです。 そのため、有料ポイントと無料ポイントは分けて管理しておいた方がよいでしょう。 このように、有料ポイントと無料ポイントを分けて管理したうえで、有料ポイントが優先して消費されるシステムとすることで、イベント開催時の有料ポイント消費を効果的に行うことができます。 とはいえ、この方法は先ほども触れたように、確実に供託義務を回避できる方法ではありません。注意してください。
4 景品表示法=価格表示やおまけの数などへの規制
 「景品表示法」は、商品やサービスの品質などの表示に関して規制を設けている法律であり、主に「景品類」に対して規制を行っています。 過剰なプレゼントサービスなども規制しており、一般消費者が自主的に、より良い商品やサービスを選択できるように主に表記などについて規制することで、消費者の権利を保護しています。
「景品表示法」は、商品やサービスの品質などの表示に関して規制を設けている法律であり、主に「景品類」に対して規制を行っています。 過剰なプレゼントサービスなども規制しており、一般消費者が自主的に、より良い商品やサービスを選択できるように主に表記などについて規制することで、消費者の権利を保護しています。
【注:事業者は景品類の提供や表示により不当に顧客を誘引しないよう適正管理義務を負う/根拠:景品表示法22条1項】
(1)有料ガチャは景品類に該当するのか
「景品類」に当てはまっている場合、「景品規制」というルールが適用されます。 「景品類」とは、以下の条件にすべて当てはまっているもののことをいいます。
- 顧客を誘引するための手段であること(顧客誘引性)
- 取引に附随すること(取引付随性)
- 経済的利益であること(経済的利益性)
それでは、一般的な有料ガチャは、これらの定義に当てはまっているのでしょうか。 消費者庁が2012年5月18日(2016年4月1日一部改訂)に発表した「オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について」によると、以下の理由で「有料ガチャ自体は、景品類に該当しない」という判断がなされています。 “有料のガチャによる経済上の利益は、事業者が有料のガチャとは別の取引を誘引するために、当該取引に付随させて、一般消費者に提供しているものではありません。” (引用:消費者庁・2012年5月18日『オンラインゲームの「コンプガチャ」と景品表示法の景品規制について』) つまり、有料ガチャは、上に示した景品類の3つの条件のうち、③を満たしてはいるものの、①②は満たしていないため、「景品類」ではないとされているのです。
なお、消費者庁は、一時期問題となった「コンプガチャ」で提供されるアイテムについては、「景品類に該当する」との判断を行っています。 そもそも、コンプガチャには、「有料ガチャで手に入るアイテムやキャラクターを揃えることで利用できる」という条件が設けられており、コンプガチャのために有料ガチャを行わなくてはなりません。 つまり、コンプガチャは、有料ガチャの利用者を集めるための手段であり(条件①)、そのために提供されている(条件②)ガチャだといえます。 また、「コンプガチャ」で提供されるアイテムは、消費者にとって、お金を払ってでも手に入れるだけの価値があるものになっていると認められるため、「経済上の利益」に当たります(条件③)。 このことから、「コンプガチャ」は「景品類」に分類されたのです。 さて、有料ガチャそのものは景品類には分類されないことがわかりましたが、景品表示法は、オンラインゲームを運営するうえで必要不可欠なプレゼントやおまけ、商品の表示・表現などに関しても、規制を行っています。
(2)プレゼント・おまけに対する規制
緊急メンテナンスやアップデート時などに無料でゲーム内ポイントを配布することがありますが、このゲーム内ポイントは「総付景品」に該当します。 ここでいう「総付景品」とは、商品・サービスの利用者や来店者に対して、もれなく提供するもののことで、「ベタ付け景品」とも呼ばれています。 総付景品は、提供できる景品の最高額について、以下のようなルールが設けられているため注意が必要です。
- 取引価額が1,000円未満の場合は、一律200円
- 取引価額が1,000円以上の場合は、取引価額の10分の2まで
このように、「取引価額」は、「1,000円以上の購入者全員に粗品をプレゼント!」などと価格に応じて総付景品を設けるときに関係してきます。 ただ、無料でゲーム内ポイントを配布する場合は、取引価額が0円という扱いになるため、配布できる最高額は、200円分のポイントまでとなります。
【法命題:ベタ付景品(同一商品付加)は値引と扱われ景品該当性の判断は「定義告示」による/根拠:景品表示法2条3項・定義告示】
(3)商品の表示・表現に対する規制
景品表示法は、商品の表示に関しても規制を行っています。 主に、以下の2つの規制が代表的です。
【注:実際より著しく優良と誤認させる表示(優良誤認)や価格等を著しく有利と誤認させる表示(有利誤認)は禁止/根拠:景品表示法5条】
- 優良誤認
- 有利誤認
①優良誤認
「優良誤認」とは、商品・サービスの品質や内容が、実際よりも著しく優良であるかのように装う表現のことです。 主に、オンラインゲームのガチャに関する表記において問題となります。 例えば、キャラクターの強化システムとして、進化→限られたキャラクターだけ最終進化という形式を採用しているゲームを考えてみましょう。 「ハロウィンガチャ!特別仕様のキャラ10体が最終進化決定!」とアナウンスしていたにも関わらず、実際に最終進化するキャラクターが3体だけで、残り7体は通常進化のみだった、という場合、実際よりも明らかに優良なサービスであるかのように表現しているため、「優良誤認」となります。
②有利誤認
「有利誤認」とは、類似商品や他社商品よりも著しく有利な取引条件であるように装う表現のことです。 こちらも優良誤認と同様、オンラインゲームのガチャの確率に関する表記において、有利誤認が問題となることがあります。 例えば、通常の出現率が0.2%の特定のキャラクターについて「期間限定!出現率5%」と書いてあるにも関わらず、実際には出現率0.2%だったガチャを考えてみましょう。 このケースでは、実際の出現率と表示されている出現率とが大きく異なっており、実際は特段有利なガチャとはいえないにもかかわらず、通常よりも特定のキャラクターを入手するために有利なガチャであるとの消費者の誤認を招く表示を行っています。 このように、利用者に著しく取引条件が有利だと誤認させる表現を「有利誤認」と呼び、景品表示法で規制を行っているのです。
(4)価格に関する表記規制
価格に関する表記では、「二重価格」表示が問題となることがあります。 例えば、ゲーム内ポイントを期間限定でセールする場合、 「通常100コイン1,000円のところ、20日まで800円!」 との表示をすることが多いのですが、通常価格とセール価格を併記していると、「二重価格表示」に当たります。 さて、二重価格表示そのものが直ちに違法というわけではありません。 しかしながら、二重価格表示には、主に以下のようなルールがあり、このルールを守れていなければ、違法となってしまうのです。
- セールス時から遡って過去8週間のうち、もとの価格で販売されていた期間が過半以上
- 販売開始から8週間未満の場合は、販売期間の過半+2週間以上の販売実績がある
- 最後にもとの価格で販売した日から2週間以上経っていない
※広告関係の法律は、「広告・マーケティングへの法律規制は?弁護士が9つのポイントを解説」の記事で詳しく解説しています。参考にしてください。
5 その他、関連する法律
 資金決済法や景品表示法以外にも、オンラインゲームを運営するうえで押さえておきたい法律がいくつかあります。 今回は、
資金決済法や景品表示法以外にも、オンラインゲームを運営するうえで押さえておきたい法律がいくつかあります。 今回は、
- 特定商取引法
- 電気通信事業法
の2つを解説していきます。
(1)特定商取引法
「特定商取引法」とは、事業者による悪質な勧誘行為を防止し、消費者の利益を守るためのルールを設けている法律です。トラブルが起こりやすい訪問販売や通信販売などのビジネスを対象に、販売方法を規制しています。 特定商取引法では、「通信販売」を、「事業者がインターネット等で広告し、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと」と定義しています。 オンラインゲームの課金は、インターネットで広告し、インターネット(通信手段)で購入の申し込みを受けるため、「通信販売」として扱われます。 そのため、特定商取引法の規制を受けることになります。 特に重要となる規制が、
- 特定商取引法に基づく表記
- 未許諾のメール広告送信禁止
- 誇大広告の禁止
の3点です。
①特定商取引法に基づく表記
特定商取引法に分類されるビジネスの場合、会社の名前や住所、電話番号、商品・サービスの価格、返品の可否などをわかりやすいところに記載しておく必要があり、この表記のことを「特定商取引法に基づく表記」といいます。 この表記を設ける理由として、顔の見えない事業者と取引を行う消費者に対して、情報をあらかじめ開示しておくことで、安心・安全に取引を行えるようにすることが挙げられます。 オンラインゲームの場合、運営会社のHPやサービスサイトに表示していることがほとんどなので、必ず作成し、掲示してください。
※特定商取引法に基づく表記については、「【テンプレート有】特定商取引法に基づく表記の書き方13のポイント」で詳しく解説しています。参考にしてください。
②未許諾のメール広告送信禁止
特定商取引法には、電子メールによる広告に関する規制(オプトイン規制)が設けられています。 「オプトイン規制」は、あらかじめ請求や承諾をしていない利用者に対し、電子メールで広告を提供することを禁止する規制です。 オンラインゲームに利用者がアカウント登録を行う場合、メールアドレスの入力を行うことがほとんどだと思いますが、事業者はそのときに入手したメールアドレスを使って、好き勝手にメール広告を送ることはできません。
メール送信に関する規制については、「メルマガを規制する法律は?2つの法律のポイントをわかりやすく解説」「名刺交換・問い合わせ対応だけで送っていい?特定電子メール法の「既存関係」の線引きと、特商法との関係、そして罰則まで」の記事も参考にしてみてください。
③誇大広告の禁止
「誇大広告」とは、実際の商品やサービスよりも、よく見せるために、著しく事実と相違する嘘や誇張表現を使用した広告のことです。先ほど解説した景品表示法の「優良誤認」「有利誤認」なども含まれています。 「誰でもガチャ100回無料」などと謳いつつ、実際には厳しい条件をクリアした人でないとガチャ100回無料で引くことはできない、などのケースが誇大広告に当たります。
【注:合理的根拠を欠く誇大表示に対しては行政による措置命令等の対象となり得る/根拠:特定商取引法6条の2以下】
【参照:不実告知・重要事項不告知による誤認の禁止/根拠:特定商取引法58条の2】
(2)電気通信事業法
「電気通信事業法」とは、電気通信ネットワークを利用して何かしらのコミュニケーションサービスなどを行う事業者に対して規制を行っている法律です。 オンラインゲームの場合、チャットやメールシステムを設けていることがほとんどですが、このチャットやメールのシステムによっては、電気通信事業者としての登録が必要となるケースがあります。 具体的には、他人から依頼を受けて、その情報の内容を変更せずに、相手に伝送する場合、「電気通信事業者」として登録・届出を行う必要があります。 例えば、携帯電話のメール機能の場合、作成したメールの本文が、そのまま相手に届きます。このようなサービスを提供する場合は、「電気通信事業者」として登録・届出を行う必要があるのです。 ただし、電気通信事業に該当したとしても、届出が不要となるケースもあります。 例えば、インターネット経由で不特定多数の利用者が文字ベースのやり取りをする「電子掲示板」や「チャット」などは、電気通信事業には当たるものの、「他人から依頼を受けて、その情報の内容を変更せずに、相手に伝送する場合」にあたらないため、電気通信回線設備を設置していない場合には、登録は必要とされていません。 一方、サイト上にチャットルームを開設し、アクセスした利用者と不特定の会話希望者とをマッチングした上で、両者間のみでやり取りする場を提供する「クローズ・ド・チャット」を行う場合は、電気通信事業者としての登録が必要となります。 どのような会話システムを設けるのか、また、設ける会話システムが電気通信事業の登録を必要とするものなのかどうか、必ず確認していきましょう。
※電気通信事業法については、「IoTサービスで注意すべき2つの法律と5つのポイントを弁護士解説」で詳しいルールや適用除外の要件などを解説しています。
6 小括
 オンラインゲームを事業として行うときは、資金決済法や景品表示法を中心とした規制が関係してきます。このほかにも、特定商取引法や電気通信事業法など、関係する規制は数多くあるため、これらをきちんと理解したうえで、対応することが求められます。 仮に、これらの規制に違反してしまうと、場合によっては、懲役刑や罰金などのペナルティを科せられてしまう可能性があることからも、自社のサービス内容との関係で適用されるルールを十分に確認しておきましょう。
オンラインゲームを事業として行うときは、資金決済法や景品表示法を中心とした規制が関係してきます。このほかにも、特定商取引法や電気通信事業法など、関係する規制は数多くあるため、これらをきちんと理解したうえで、対応することが求められます。 仮に、これらの規制に違反してしまうと、場合によっては、懲役刑や罰金などのペナルティを科せられてしまう可能性があることからも、自社のサービス内容との関係で適用されるルールを十分に確認しておきましょう。
(補足)アプリ内課金(Apple/Google)と法対応の両立
アプリ内課金(IAP)は各ストア審査ポリシーの適合が前提です。ポイント/通貨設計が「前払式支払手段」に該当する場合の掲示義務・供託トリガー、有効期限の設定、無料/有料ポイントの区分管理などは本稿のルールと整合させる必要があります。ストア外決済や外部リンク誘導が制限される場面もあるため、(1)IAPの範囲、(2)決済導線の文言、(3)約款・表記(特商法/資金決済法)の三点を同時に詰めるのが実務上のコツです。
7 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- オンラインゲームの課金は、「資金決済法」で規制されている
- ゲーム内ポイントは、「アイテムを入手するために、事前にお金を変換しておくポイントやコイン」などに該当するため、前払式支払手段である
- 前払式支払手段の発行者には、主に、①情報の提供義務、②発行保証金の供託義務という2つの義務が課される
- 「発行保証金の供託義務」は、毎年3月末か9月末に、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えていたときに、その半分の額を供託所(法務局など)に預ける義務である
- 発行保証金の供託義務を回避する方法としては、①前払式支払手段に有効期限を設ける、②ポイント消費を促すイベントを開催するなどがある
- おまけの数や価格表示、商品表示は「景品表示法」で規制される
- 一般的な有料ガチャそのものは景品類に該当しないものの、コンプガチャについては、景品類に該当する
- 総付景品は、提供できる景品の最高額について、①取引価額が1,000円未満の場合は一律200円、②取引価額が1,000以上の場合は、取引価額の10分の2まで、というルールが設けられている
- 景品表示法では、商品の表記について、①優良誤認、②有利誤認などの表現を規制している
- オンラインゲームの課金は「通信販売」に当たるため、特定商取引法による規制を受ける
- 特定商取引法では、①特定商取引法に基づく表記、②未許諾のメール広告送信禁止、③誇大広告の禁止などに注意が必要である
- 利用者同士のコミュニケーションツールを設ける場合は、電気通信事業法のルールを確認しておく必要がある