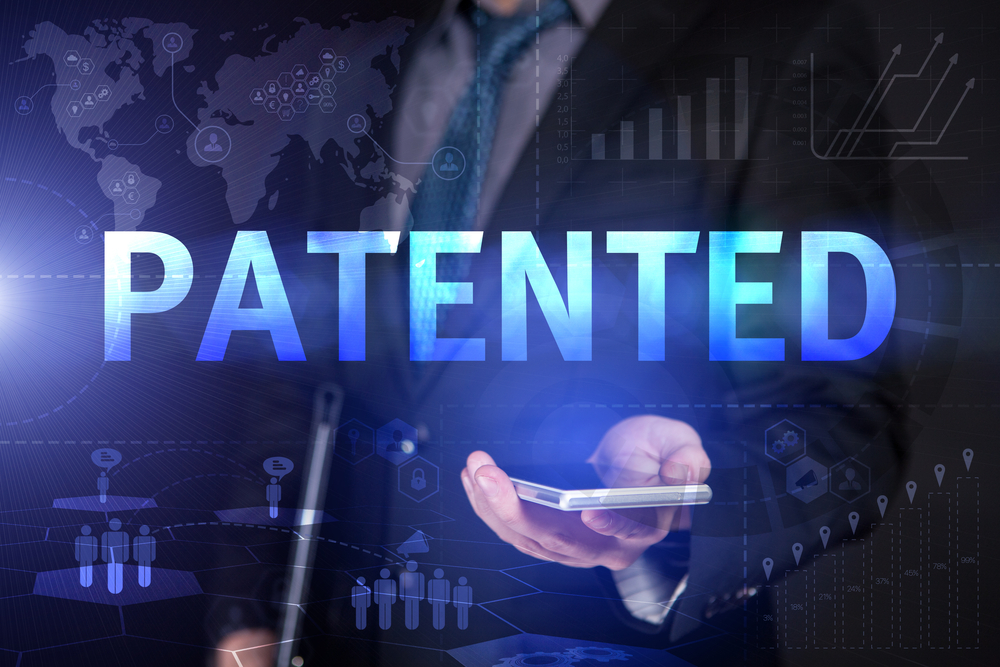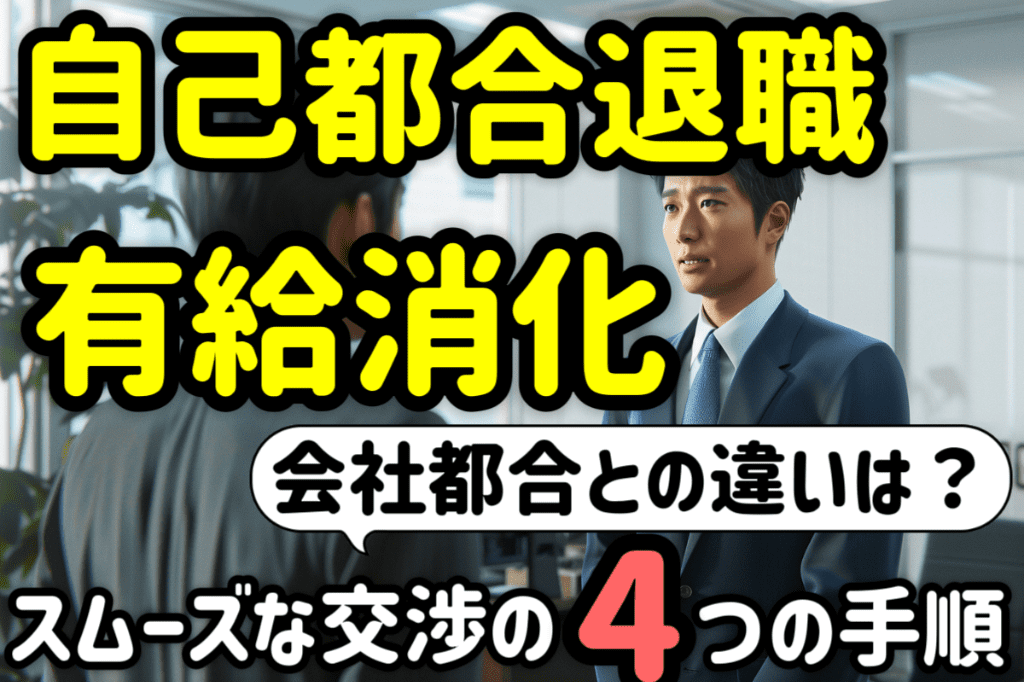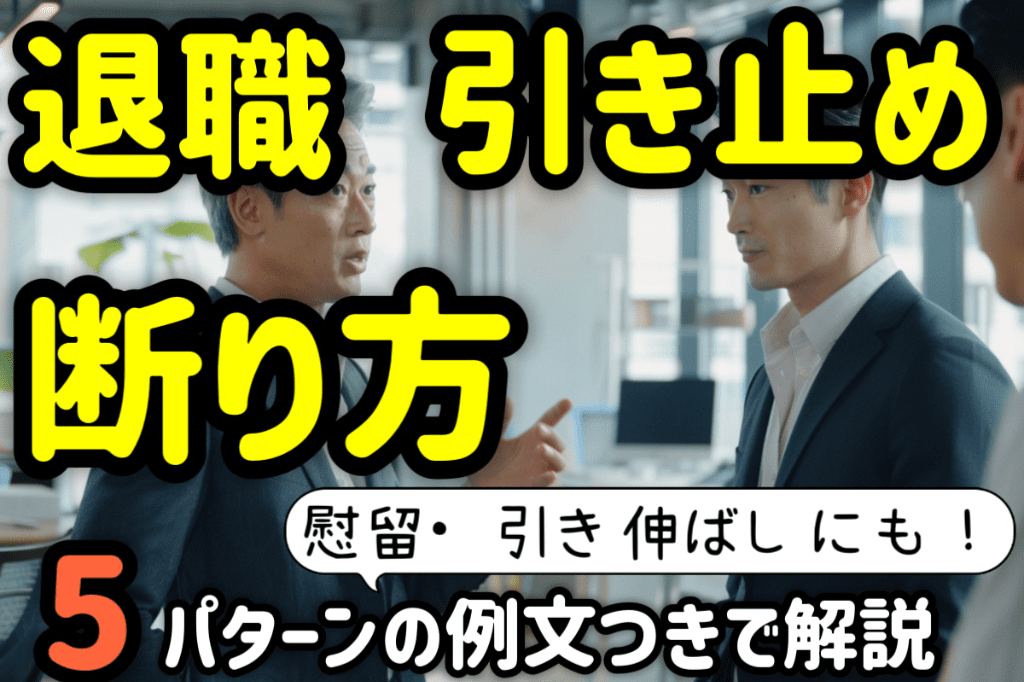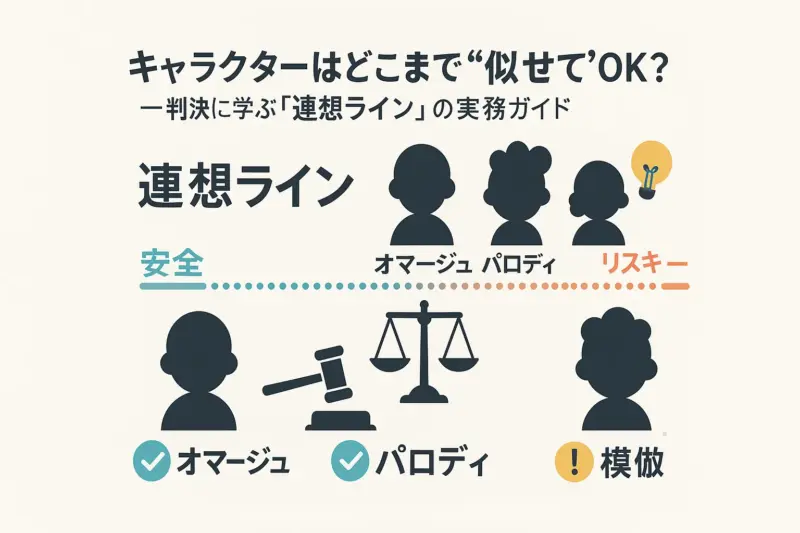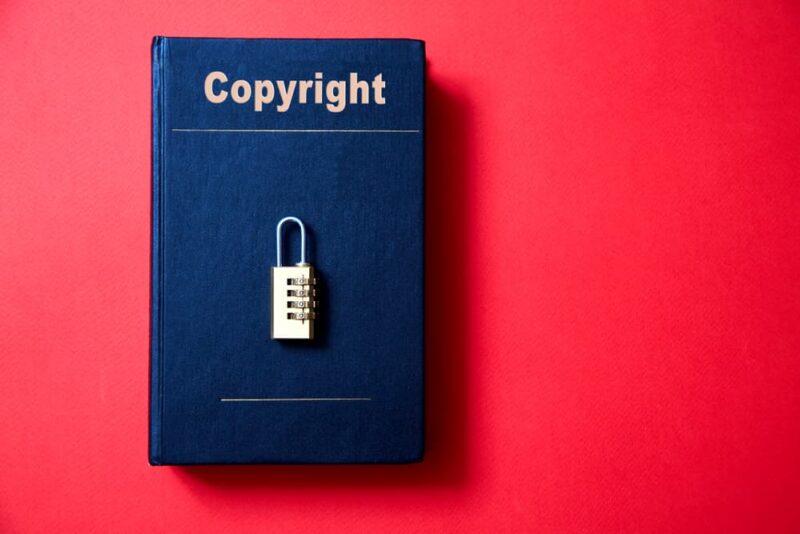著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール

はじめに
自分のwebサイトやブログ上に、ネットで転がっている他人の画像や文章を転載する際に、「これって著作権侵害にならないかな?大丈夫かな?」と不安を持つ方は多いのではないでしょうか?
この点については、著作権の「引用」という条件をみたせば違法にならないのですが、具体的にどういう場合に引用の条件をクリアできて、反対に、どういう場合に引用にならず違法になってしまうのか、正直よくわからないですよね。
そこで今回は、うっかり他人の著作権を侵害しないために、画像・文章などに認められる著作権の内容、「引用」の条件・ルールや、著作権侵害をしてしまった場合のペナルティなどについて詳しく解説していきます。
この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之
- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務
GWU Law LL.M.(知的財産法)
事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら
1 著作権とは

まず、著作権とは何なのか、どのようなものに関係する権利なのかを説明します。
人が独自に創り出した画像や文章などの表現物を「著作物」といい、その著作物を作った人のことを「著作者」といいます。
そして、著作物が他の人に無断で利用されたり転載されたりしないように、著作者を法的に守ってくれる権利のことを「著作権」といいます。
画像や文章などにこの著作権が認められると、無断でこれらを転載したり利用することは「著作権侵害」として違法になります。
2 著作権侵害で違法にならないケース

ただし、他人が作った画像や文章など利用したとしても、すべてのケースで違法になるわけではありません。表現物の利用をあまりに制限してしまうと、とても窮屈な世界となって、日本のコンテンツ産業・文化の発展も妨げることになります。
そういった事情を考慮して、著作権法では、「引用」も含め、以下のケースに当てはまる場合には、例外的に他人の表現物(コンテンツ)を使っても「著作権侵害」とならず、違法ではないとしています。
- そもそも著作物ではない
- 著作者の許可を得ている
- 引用
- 転載が許される場合(著作権法32条2項、39条、40条)
「引用」に限らず、この4つのいずれかにあてはまる場合には、著作権侵害になりません。そのため、皆さんが一番気にしている「引用のルール・条件」に飛びつく前に、まずは以下のフローで検討するのが大事です。

順番に確認していきましょう。
(1)そもそも「著作物」ではない場合
他人の画像や文章を転載して著作権侵害になるのは、その前提として、あくまでもその画像などが「著作物」として保護されている場合に限ります。
そのため、落書きなどの「著作物」とは評価できないものを転載したとしても、もとより合法であるため、「引用」などはそもそも検討する必要がありません。
「著作物」とは、先に説明したとおり、オリジナリティのある表現物のことですが、厳密にいうと、以下の条件「1.2.3」をすべて満たすものをいいます。
- 「思想または感情」が表れていること
- 作者の「個性」が表れていること
- 「表現」されたものであること
そのため、これら「1.2.3」のいずれかの条件を欠く以下のようなコンテンツは「著作物」にあたらず、「引用」の条件をみたすまでもなく、合法的に利用できます。
【著作物にあたらない場合】
①ありふれた表現や題名、ごく短い文章
②歴史的事実やデータ
③事実の伝達にすぎない時事報道など
④プログラム言語やアルゴリズム(解法)
⑤保護期間の満了した著作物
⑥アイデア
⑦実用品のデザインなど
①ありふれた表現や題名、ごく短い文章
「日頃のご愛顧に感謝いたします。」や、「厳しい暑さが続きますが、いかがお過ごしでしょうか。」などの表現は世の中にありふれたものであって、「2.作者の個性が表れていること」という条件をみたさないため著作物にはあたりません。
②歴史的事実やデータ
「徳川家康は、1603年に江戸幕府を開いた。」という史実のような、単なる歴史的事実やデータは、「1.思想または感情が表れていること」という条件をみたさないため、著作物にあたりません。
③事実の伝達に過ぎない時事報道など
例えば絵画の窃盗事件があった場合には、どのような絵画が盗まれたのかを正確に報道する必要があります。このように、正確な報道をするために著作物の利用が必要な場合があり、これを新聞に掲載したりニュースで報道したりしても著作権侵害にはなりません。
④プログラム言語やアルゴリズム(解法)
著作権法は、表現それ自体を保護するものなので、表現方法としてのプログラム言語やアルゴリズムについては「3.表現されたものであること」という条件をみたさず保護されません。
⑤法律、通達、裁判所の判決など
法律や通達、判決などは、私たち国民の生活に大きな影響を与えるものです。そのため、これらは国民全体に広く知らしめる必要があり、自由に利用できるよう例外的に著作権の保護対象とはなっていません。
⑤保護期間の満了した著作物
著作物の保護期間は、著作者の死後70年までです(著作権法51条2項)。そのため、それ以降は著作権によっては保護されません。
映画の著作物の保護期間は、公表後70年までです(著作権法54条1項)。創作後70年以内に公表されなかった場合には、創作から70年が保護期間になります。
これらの期間が経過した後は、著作権による保護はなくなります。
⑥アイディア
アイディアは、頭の中で考えている段階ではそれ自体を他人が知ることはできないため、「3.表現されたものであること」という条件をみたさず、著作物にはあたりません。ただし、そのアイディアを書いた本などは著作物にあたります。
⑦実用品のデザインなど
一般的には、家具や家電、衣服などの実用的なデザインについてはそもそも著作権では保護されません。そのかわり、実用的なデザインの保護については意匠権という制度があり、意匠として登録されているデザインを勝手に使うと意匠権侵害や不正競争防止法の問題となることがあります。
(2)著作権者の許可を得ている場合
著作物については、無断で利用した場合には違法となりますが、あらかじめ著作者に許可をとっていれば著作権侵害にはなりません。
なぜなら、著作権は、著作者を保護するための権利なので、その権利者が「使ってOK」と明確に許可しているところで、これを違法とする必要がないからです。
もっとも、以下の2点には留意が必要です。
一つは、その著作物を利用できる範囲は、著作者が明確に利用を許可した範囲に限られますので、許可の範囲を超えて利用した場合には、やはり違法となります。
例えば、ある画像の著作者が「アダルト以外のサイトに掲載してもOK」という条件で利用を許可したにもかかわらず、アダルトサイトにその画像を掲載した場合には、許可の範囲を超えるものとして、違法になります。
二つめは、「著作者」と「著作権者」が違う場合があることです。
著作者が著作権を他人に譲り渡している場合があるため、その場合に著作者の許可を得たところで「著作権者の許可」を得たことにはなりません。必ず現在の著作権者から許可を取ってから利用する必要があります。
それでは次の項目で、引用のルールや条件について詳しく見ていきましょう。
3 「引用」のルール・条件とは

「引用」とは、他人が作った著作物を、自分の表現物(コンテンツ)に取り入れることをいいます。引用といえば文章というイメージかもしれませんが、画像や動画も引用することが可能となっています。
さて、先ほども説明したように、著作物の無断利用は原則として違法になりますが、「引用」が成立する場合には、他人の著作物を無断で利用する場合でも、違法になりません。
「引用」という例外が認められる理由は、人が何かを主張したり批判するなど、自由な言論のためには他人の著作物を用いる必要性の高い場面がたくさんあるため、利用を制限しすぎるのは問題だからです。
例えば、何か自論を展開しようとしたときなど、その根拠として誰かの文章を引用すれば、より説得力や信頼度が増しますよね。これに応えたものが「引用」のルールなのです。
そして、「引用」が認められるためには、次の条件をすべてみたす必要があります。
- 主従関係が明確であること(明確性)
- 引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
- 引用をする必要性があること(必要性)
- 出典元が明記されていること(出典)
- 改変しないこと
これら①~⑤のすべての条件ををみたさなければ、「引用」は成立せず、原則どおり違法となります。
それでは、それぞれの項目の内容について詳しく見ていきましょう。
(1)条件①:主従関係が明確であること(明確性)
「主従関係」とは、作成しているコンテンツついて量的にも内容的(質的)にも、オリジナル部分がメインであって引用部分はあくまでも補足でなければならないというものです。
引用する量が多くなると主従関係が逆転してしまい、この条件をみたすことができなくなってしまいます。引用部分はあくまでも「根拠」を示すためのものであるということを忘れないようにしましょう。
では、具体的にどのような場合であればオリジナル部分と引用部分の主従関係が成立しているといえるのでしょうか?
まず、引用部分に比べてオリジナル部分が少ししかなかったり、創作性のないものである場合、これは正当な引用とは認められません。
もし作成したコンテンツ内のほとんどが引用部分だった場合には、原則どおり著作権侵害になるため注意が必要です。
実際の裁判例でも、有名サッカー選手の詩を無断で「引用」し、オリジナル部分についてはたった2文しか掲載していなかったケースで、裁判所が著作権侵害を認定したものがあります。
「なるほど。主従関係っていうんだからオリジナル部分が引用部分より多ければいいんでしょ?じゃあ6:4で!」
これもダメです。この点については、引用部分の割合は全体の1割程度までにとどめることが推奨されています。
つまり、引用として認められるためには、オリジナル部分と引用部分との間に圧倒的な差が必要だということです。
(2)条件②:引用部分が他とはっきり区別されていること(明瞭区別性)
「明瞭区別性」とは、オリジナル部分と引用部分とが明確に区別されていることをいいます。簡単に言えば、他人の文章や画像をあたかも自分が書いたり撮影したかのように掲載することはダメだということです。
どのように他人の画像や文章と区別すればいいのかというと、次のような方法があります。
- 引用部分を“”(ダブルクォーテーション)や「」(カギかっこ)ではさむ
- 文字そのものを斜体や太字にしたり色を変える
- 引用部分の背景色を変える
- 引用部分から改行して行頭を一段下げる
- 引用部分を枠で囲ったり背景に画像を使う
- blockquote(ブロッククォート)タグ(HTMLタグ)を使う
要するに、引用部分が一目で分かるようにしなければならないということです。
引用の具体的なやり方については、「4 引用の書き方・方法」で説明します。
(3)条件③:引用する必要性があること(必要性)
「必要性」とは、その著作物を引用する必要が本当にあるのか?ということです。
つまり、記事などを書くうえで、「他人の著作物を引用しなければ説明ができない」という状況でなければなりません。そのため、単純に「この人の画像や動画を自分のコンテンツに載せたい!」という理由だけでは引用はできないことを理解しておく必要があります。
具体的には、例えば、ある絵画の作品について批評がしたい場合、その絵がどんなものなのか分からないと読み手には何も伝わらないですよね。
このような場合にはその絵画について引用の必要性があるということができます。
一方、ある本について批評をしたい場合、その中身である文章については引用の必要性があるといえますが、本の表紙については批評に関係がない(引用しなくても批評として成立する)ので引用することはできないと考えられます。
(4)条件④:出典元が明記されていること(出典)
これは文字どおり、その引用部分をどこから持ってきたのか、情報源(ソース)を明確にしなければならないということです。
本の内容を引用したのであればその本の名前を、Webサイトから引用したのであればそのサイト名やURLを記載します。その理由は、著作物は著作権によって守られているため、それが引用であることを明らかにするのが望ましいからです。
こちらも、具体的には「4 引用の書き方・方法」で説明します。
(5)条件⑤:改変しないこと
最後に、他人の著作物を引用するときは、手を加えずにそのまま引用しなければなりません。長文を引用する際に、文字数などの関係でどうしても「要約」せざるを得ないこともありますが、原文の意味や趣旨が変わって伝わるような恣意的な要約は違法になるため注意が必要です。
以上の(1)~(5)の条件をすべてみたせば、「引用」が成立し、他人の著作物を無断で利用したとしても著作権侵害にはあたらず、違法になりません。
4 「引用」の書き方・方法

それでは、具体的に他人の著作物を引用する場合の書き方(方法)・注意点をみていきましょう。
(1)オリジナル資料から直接引用する
まず、引用するときには必ずオリジナルの資料(著作物)から引用しましょう。
すでに引用されたものをさらに引用することを「孫引き」といいますが、これは違法になるリスクが残るため、できるだけ避けてください。
なぜかというと、引用の対象としたサイトが適法に「引用」ができておらず違法な場合、それを孫引きした自分も連作的に違法になってしまうからです。
また、自分で直接確認していない情報をそのまま引用することは、コンテンツの信用性を下げてしまいます。
そのため、引用したい情報がすでに引用されたものであった場合は、その原典を探して原文から引用しましょう。
(2)引用部分の区別
先ほど説明した引用部分の区別の仕方を具体的にみていきましょう。
-
- 引用部分を“”(ダブルクォーテーション)や「」(カギかっこ)ではさむ
例:“吾輩は猫である”、「吾輩は猫である」
-
- 文字そのものを斜体や太字にしたり色を変える
例:吾輩は猫である、吾輩は猫である、吾輩は猫である
-
- 引用部分から改行して行頭を一段下げる
例:〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
吾輩は猫である
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
-
- blockquote(ブロッククォート)タグ(HTMLタグ)を使う
例:
吾輩は猫である。名前はまだ無い。
(3)引用元を明示、リンクを貼る
先ほども説明したとおり、引用する際は必ず「引用元(情報源、ソース)」を示さなければなりません。
- 文章を引用するときの例:〇〇〇〇より引用
- 画像を引用するときの例:参照:〇〇〇〇
また、引用する文章や画像、写真がWeb上のものの場合には、引用元の情報を示すだけでは不十分です。
引用元の情報に加えて、そのコンテンツへ飛べるリンクも用意しておく必要があります。
これによりどこから引用してきたのか明らかになり、引用元のコンテンツも確認することができます。
(4)実際に「引用」する際のイメージ
引用する際には当然、先ほど説明した引用のルールをきちんと守ることが必要です。
もう一度確認しましょう。
- 主従関係が明確であること(明確性)
- 引用部分が他とはっきりと区別されていること(明瞭区別性)
- 引用をする必要性があること(必要性)
- 出展元が明記されていること(出典)
- 改変しないこと
これらの点に気を付けながら、実際に引用してみると以下のようになります。
①文章を引用する場合の実例
文章を引用する際の実例を見てみましょう。
※便宜的に、弊社トップコートが書いた、他の法律コンテンツを例に説明します。
- 原文:「仮想通貨」(暗号通貨、バーチャルマネー)とは、Webサービス上でのみで使える購入型のポイントや、実際の紙幣や貨幣が存在しない、文字どおり仮想の通貨のことをいいます。
この原文を引用する際には、以下のように blockquote(引用タグ)処理をして明確に引用先のコンテンツと区別し、そのうえで、引用先のサイト名をテキストリンクを付して、出典先として記載しておきます。
「仮想通貨」(暗号通貨、バーチャルマネー)とは、Webサービス上でのみで使える購入型のポイントや、実際の紙幣や貨幣が存在しない、文字どおり仮想の通貨のことをいいます。
②画像・写真を引用する場合の実例
画像や写真を引用する場合を確認してみましょう。
よくあるダメな例として、ほとんどの人は他人の作った画像や写真を載せて、出典先を記載するだけで終わらせてしまっています。
しかし、先ほど書いたとおり、引用のルールはすべてみたさなければならないため、引用元の情報を載せるだけでは不十分ということになります。
画像や写真の場合も文章のときと同じように、引用部分をオリジナル部分と区別する必要があるため、以下のように掲載しましょう。

5 転載が許される場合

引用と似た概念に「転載」があります。「転載」とは、他人の著作物の大部分を複製・コピーして利用する行為のことをいいます。引用のレベルを超えたものが転載、という認識でオッケーです。
引用は、一定のルールを守れば、著作者から許可を得ることなく著作物の利用をすることができましたが、転載は、著作者からの許可がある場合のみ可能となります。言い換えると、転載は、著作者に無断で行うことは許されません。
もっとも、一定のケースでは、著作者の許可なく転載することが許されます。
具体的には、以下の3つは無断転載が可能です。
- 行政機関が公表した広報資料など
- 新聞や雑誌に掲載された、時事問題に関する論説
- 政治上の演説・裁判上の陳述
それぞれの条件を順番にみていきましょう。
(1)行政機関が公表した広報資料など
行政機関が一般に公開した資料は、転載することができます。
転載条件は以下のとおりです。
- 行政機関の名前で公表した資料であること
- 一般に周知させることを目的とした資料であること
- 転載を禁止する旨の表示がないこと
- 説明の材料として利用すること
(2)新聞や雑誌に掲載された論説
新聞や雑誌に掲載された論説のうち、学術的でないものは転載することができます。
転載の条件は以下のとおりです。
- 新聞または雑誌に掲載された論説であること
- 政治・経済・社会上の時事問題に関する論説で、学術的な性質ではないものであること
- 他の新聞や雑誌への転載、放送、有線放送として利用すること
- 転載・放送・有線放送を禁止する旨の表示がないこと
(3)政治上の演説・裁判上の陳述
政治上の演説や裁判上の陳述も、転載することができます。
転載の条件は以下のとおりです。
- 公開して行われた演説・陳述であること
- 同じ著作者の物のみを編集して利用しないこと
これら3つは、著作者の許可を得ることなく転載することができます。その場合、それぞれの条件をきちんと守るのはもちろんのこと、出所の明示も忘れずにすることがポイントとなります。
6 著作権侵害のペナルティ

最後に、もしも著作権侵害をしてしまった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか?
著作権を侵害してしまった場合には、
- 民事上のペナルティ
- 刑事上のペナルティ(罰則)
の2種類のペナルティがあります。
(1)民事上のペナルティ
著作権侵害があった場合、著作者は、侵害した人に対して以下のような請求をすることができます。
- 差止請求(侵害の停止または予防を請求すること)
- 損害賠償請求(侵害により発生した損害を賠償請求すること)
- 不当利得返還請求(侵害によって得た利益を返すように請求すること)
- 名誉回復等の措置請求(謝罪広告掲載など、名誉の回復を求める請求をすること)
損害賠償については、弊所記事「著作権侵害の警告が届いたらどうする?アクセス数がゼロでも損害賠償を払う必要があるの?」も参考にしてみてください。
(2)刑事上のペナルティ(罰則)
肖像権侵害やパブリシティ権侵害と違って、著作権侵害は犯罪行為です。
この場合、親告罪といって、被害者である著作権者が訴え出ることによって侵害者を処罰することができます。
ペナルティの具体的な内容としては、
- 最大10年の拘禁刑
- 最大1000万円の罰金
のいずれか、または、両方で処罰される可能性があります。
また、両罰規定といって、法人の代表者や従業員が侵害行為をした場合、行為者だけではなくその法人自体に対しても
- 最大3億円の罰金
が科されます。
さらに、利用した著作物の出所をきちんと示さなかった場合にも
- 最大50万円の罰金
があります。
ただし、刑事罰(罰則)が科されるのは、故意(わざと)に著作権を侵害した場合のみであって、ついうっかり(=過失)著作権侵害をしてしまった場合には、刑事罰(罰則)が科されることはありません。
とはいえ、著作権を侵害する行為が犯罪行為であることに変わりありません。
多くの方は意外に思われるかもしれませんが、著作権侵害は罰則が設けられているくらい重大なルール違反なのです。他人のコンテンツを利用する際には、ペナルティの内容を踏まえたうえで、違法にならない形で利用しましょう。
7 他の注意点~肖像権・パブリシティ権~

自社のオウンドメディアやwebサービスを構築していくうえで、他人の画像や文章を利用する場合には、著作権の「引用」ルール以外にも、近年トラブルの多い肖像権やパブリシティ権などにも気を付けなければなりません。
以下で順番にみていきましょう。
(1)肖像権について
他人の顔や容姿が写りこんだ画像や写真を利用する場合に問題となるのが「肖像権」です。
「肖像権」とは、自分の顔や姿を無断で写真撮影されるなどして公表されない権利のことをいいます。
勝手にスマホで写真撮影されて、それがネット上に公開されたら、自分のプライバシーがのぞき見された気がしてなんだか気持ち悪いし嫌ですよね。このような事態を防ぐために認めらているのが肖像権になります。
肖像権の侵害に当たるかどうかは、対象となる画像や映像の内容、使用方法、撮影場所、撮影方法などの事情を考慮して判断します。
具体的には、以下のような事情著作権を侵害しているかどうかを検討します。
- 特定の人をメインに撮影したものでその画像や映像からその人が特定可能かどうか
- 写真や映像を、拡散されやすい場所に公表しているかどうか
- 写真や映像が公表されたことによって、そこに写っている人に精神的なダメージを与えるかどうか
- 写真や映像に写っている人から、撮影・使用の許可をとっているか
例えば、ある人が単体で写真に写っていて、その人の特定が可能な場合に、これをネット上のブログなどに掲載すれば、肖像権侵害となる可能性が高くなります。これは最近SNS上でよくトラブルになる典型的なパターンです。
このように、「知らない間に肖像権侵害をしてしまっていた・・・」という事態を防ぐために、以下の点に気を付けましょう。
①本人の同意をとる
著作権の場合と同じように、本人の許可があれば肖像権侵害にはなりません。
撮影することについてだけではなく、公表すること・その範囲についても同意を得ておくことをお勧めします。
②写真を加工する
人物の特定ができなければ肖像権侵害にはならないので、モザイクや黒塗りで画像処理をしましょう。
事前にも事後にも本人から許可を得られなかった場合に有効な手段です。
仮に肖像権を侵害してしまったとしても、刑事上のペナルティはありません。
ただし、権利侵害をされた本人から民事上の損害賠償請求や利用の差し止め請求をされる可能性はあります。
トラブルを避けるためにも、他人が映り込んでいる画像を利用する場合には細心の注意を払いましょう。
(2)パブリシティ権について
他人、特に芸能人が写りこんだ画像や写真を利用する際に、肖像権とは別個に注意しなければならないのが「パブリシティ権」です。
「パブリシティ権」とは、芸能人などの著名人に認められる権利で、顧客吸引力のある肖像(顔や容姿)や名前などを利用できる権利のことをいいます。
タレントやアイドル、スポーツ選手などはその顔や名前に宣伝効果がありそれだけでお金を稼ぐことができますよね。
パブリシティ権とは、この「お金を稼ぐ力」(=財産的価値)を他人に勝手に利用されない権利のことをいいます。
タレントなどの「商品としての価値」を守るためにこのような権利が認められています。
肖像権とパブリシティ権は撮影対象者に認められた権利という点でよく似ていますが、その違いは、①守られている対象が一般人か著名人かという部分と、②人格的な利益を守るのか経済的な利益を守るのか、という点にあります。
パブリシティ権を侵害するかどうかの基準については、裁判例では、芸能人などの肖像を無断で利用した場合であっても、すぐに違法とはなりません。
肖像を無断で利用した、その利用者の「目的」にフォーカスして、「他人の氏名、肖像権の持つ顧客吸引力に着目し、もっぱらその利用を目的とするものであるかどうかにより判断すべき」とされています(ピンクー・レディ事件判決)。
例えば、タレントの写真を勝手に広告に使ったり、グッズを作成して販売するなどした場合には、明らかにパブリシティ権の侵害にあたります。
このように、タレントの力を使ってお金を稼ごうとしているかどうかがパブリシティ権侵害かどうかを判断するうえで重要な事実です。
しかし、商業目的でなくても、個人的に特定のタレントを応援するためブログに写真を掲載しているような場合で、タレントの力によって閲覧者をそのブログに誘導していると認められるようなケースは、パブリシティ権の侵害になってしまう可能性が高いため注意が必要です。
パブリシティ権の侵害については、肖像権と同じく刑事上のペナルティはありません。
ただし、こちらも同じくタレントの事務所やプロダクションなどからの民事上の損害賠償請求や差し止め請求をされる可能性があります。
賠償金額は、一般人の肖像権侵害に比べて莫大なものになることが予想されます。
そのため、許可なくむやみに著名人の写真や名前を使うのは控えた方がいいでしょう。
8 小括

著作物の引用について、細かいルールがたくさんあることを理解していただけたでしょうか。このルールをきちんと理解していなければ、知らないうちにうっかり他人の著作権を侵害してしまっていた、なんてことにもなりかねません。
また、軽い気持ちで著作権侵害をしたとしても、そのペナルティはかなり重くなっています。
今回解説した内容を理解し、他人の著作物を利用するときには著作権法のルールに違反しないかをしっかりと確認することが大切です。
9 まとめ
これまでの説明をまとめると、以下のようになります。
- 「著作権」とは、著作物が他人に無断で利用されないように、著作者を法的に守っている権利のこと
- 著作権のある画像や文章を無断で利用・転載すると、著作権侵害として違法になる
- ただし、①そもそも著作物でない場合、②あらかじめ著作者から許可を得ているような場合、③引用、④転載(著作権法32条2項)の場合、その利用は違法にはならない
- 「引用」の条件として、①明確性、②明瞭区別性、③必要性、④出典の明記、⑤改変しないこと、という5つがある
- 著作権以外にも、肖像権やパブリシティ権に注意する
- 「転載」とは、他人の著作物の大部分を複製・コピーして利用する行為のことで、著作者に無断で行うことは許されない
- ただし、①行政機関が公表した広報資料、②新聞や雑誌に掲載さ入れた時事問題に関する論説、③政治上の演説・裁判上の陳述については無断転載が可能
- 著作権侵害のペナルティはとても重い
IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。