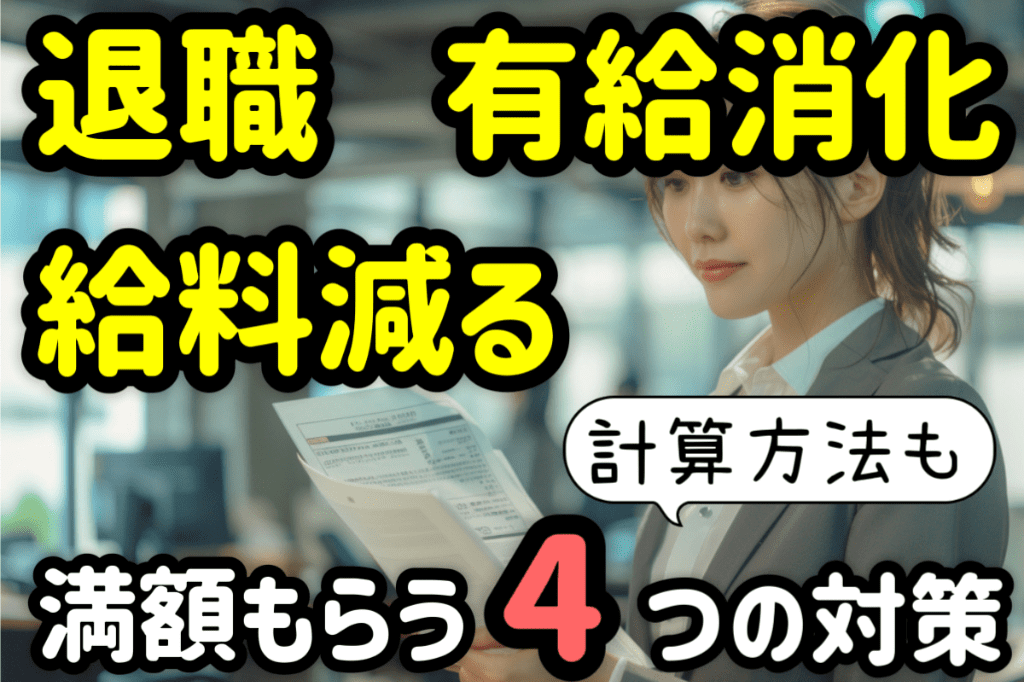著作権侵害にならない方法は?著作物の利用の悩みを解決する5つの案

はじめに
他人に文章やイラスト、BGMを作成してもらう、写真を撮影してもらうことはよくある話です。
これらのコンテンツを利用する際に、著作権侵害となって懲役や罰金などを負いたくはないですよね。では、著作権侵害にならない方法はあるのでしょうか。
この記事では、著作権侵害にならない形でコンテンツを利用したい方向けに、著作権侵害にならない方法について、弁護士が解説をしていきます。
1 著作権侵害にならない場合とは
著作権侵害にならない場合とは、どのようなケースが当てはまるのでしょうか。
ここではまず「著作権」や「著作権侵害」とはなにかをおさらいし、次に「著作権侵害にならない5つの場合」について見ていきましょう。
(1)著作権侵害とは
①著作権とは
「著作権」とは、著作物を独占的に利用できる権利のことをいいます。
著作物を作成した時点で自然と著作者に権利が発生するので、権利を得るために特別な手続きは必要ありません。この著作権を持つ者を「著作権者」といいます。もっとも、著作権は、譲渡や相続が可能です。そのため、著作者と著作権者が一致しないこともあります。
②著作権侵害とは
「著作権侵害」とは、「著作権者」の許諾を得ずに著作物を、コピーしたり、翻訳・加工(翻案)したり、それらをインターネットで公開したり、譲渡や販売などをしたりといった形で利用することをいいます。著作物の全部ではなく一部だけを利用した場合も侵害となってしまう可能性があります。
著作権者は侵害者に対して、差止請求や損害賠償請求をすることができます。
また、著作権侵害には、罰則があり、場合によっては、
- 最大10年以下の懲役
- 最大1000万円以下の罰金
のどちらか、またはその両方が科される可能性があります。
これらの請求や罰則を受けないためには、著作権侵害にならないようにコンテンツを利用しなければいけません。
(2)著作権侵害にならない5つの場合
著作権侵害にならないのは以下の5つの場合です。
- そもそも著作物ではなかった場合
- 著作物であっても著作権がない場合
- 権利者から利用の許諾を得た場合
- 権利を譲り受けた場合
- 許諾を得ることなく利用できる場合
それぞれの詳細について、以降の項目で確認していきましょう。
2 そもそも著作物ではなかった場合
著作権は、著作物を独占的に利用できる権利です。そのため、そもそも利用したコンテンツが著作物ではないということになれば、著作権の侵害にはなりません。
著作物として認められるのは、生み出したコンテンツなどが下記の要件を満たしている場合です。
- 思想または感情が表れていること
- 著作者の個性が表れていること
- 表現されたものであること
- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること
この条件だけでは、何が著作物になるのか、よくわからないかもしれません。著作物の具体例については、以下の表を御覧ください。
上の表に載っていても、4つの要件のどれか1つでも当てはまらないものがあると、著作物ではなくなります。
たとえば「東京には23区がある」、「富士山の高さは3776メートル」、「フライパンで溶き卵を焼くと卵焼きができる」などといったものは、事実の指摘や単なるデータにすぎません。これらの内容を講演したとしても思想や感情を伴っていないため、著作物にはあたりません。
また、アイデアや企画を頭の中で思い浮かべているだけでは著作物にはなりません。なぜなら、アイデアや企画の段階では、まだ、思想や感情、個性が表現されていないからです。
このように、著作物の4つの要件を満たしていない=「著作物ではない」といえるものを利用する場合には、著作権が発生していないため、基本的に著作権侵害を心配する必要はありません。
では、著作物にあたるものを著作権侵害にならないで利用するためには、どうしたらいいのでしょうか。以降の項目で確認していきましょう。
3 著作物であっても著作権がない場合
原則として、著作物であれば著作権者が著作権を持っていることになりますが、例外的に著作物であっても著作権がないケースもあります。
以下の2つがこの例外的なケースです。
- 法律、国や自治体の通達、裁判所の判決やこれらの編集物
- 著作権の保護期間が切れたもの
(1)法律、国や自治体の通達、裁判所の判決やこれらの編集物
以下について、その文章や文言を考えた人の思想や感情を個性的に表現したものとして、著作物にあたります。もっとも、国民に広く周知させる必要があるものなので、例外的に著作権が発生しないことになっています。
- 憲法やその他の法令
- 国等が発する告示・訓令・通達等
- 裁判所の判決等
- 国等が作成した①~③の翻訳物や編集物
著作権がないため、これらは、自由に利用ができることになっています。
なお、④は、国等が作成する、いわゆるガイドラインや広報用の冊子やパンフレットなどです。
民間業者等が法律のガイドラインの解説を作成してWebサイトに記事として掲載したり、書籍を出版して販売したりすればその記事や書籍に著作権が発生します。国等が作成していない著作物を無断で利用すると著作権侵害になるためご注意ください。
(2)保護期間が切れたもの
著作権という権利は、永久的に保護されるわけではなく、保護期間というものが決まっています。
保護期間が切れた著作物には、著作権がありません。著作権が切れた後は、社会全体の公共の財産として自由に使える著作物となります。
日本においては、2018年に著作権法の改正があり、保護期間はこれまでの著作者の死後50年から70年に延長されました。
そのため、50年のままであれば著作権の保護期間が切れていたはずの作品も延長により保護期間が延びています。「作者の死後50年経っているからそろそろ保護期間が終わっているはず」と保護期間を勘違いしていると、思わぬところで著作権侵害となってしまうため、ご注意ください。
また、海外の著作物を使用する場合は、国によって保護期間が異なることがあるほか、その国の法改正で保護期間が延長していることもあります。たとえば米国では、ウォルト・ディズニーの『ミッキーマウス』の著作権保護期間が終了する直前、さらに20年の延長を認めた経緯があります。
このように、著作物であっても著作権がない場合、著作権侵害にはなりません。もっとも、誰がその著作物を生み出したのか、いつまでが保護期間なのかきちんと確認することを徹底する必要があります。
では、国等が作った著作物ではなく、保護期間も切れていない場合に、著作権侵害にならないように著作物を利用するためには、どうしたらいいのでしょうか。
このような場合には、著作権者から利用許諾を得るという方法があります。
4 権利者から利用の許諾を得た場合
著作権侵害とは、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用したり、コピーや翻訳・加工(翻案)をしたり、それらを公衆送信したり、譲渡や販売などをしたりすることでしたね。
そのため、著作権者から利用許諾を得ていれば、著作権侵害にならずに著作物を利用することができます。
もっとも、「許諾を受ければ後は好きに使って良い」というわけではありません。あらかじめ許諾を得た利用の範囲を超えた場合は著作権侵害になってしまいます。
利用方法や条件、使用料などについては各著作権者によって異なりますので、使いたい著作物の著作権者に問い合わせてみましょう。
また、著作権者から利用許諾を得る場合には、トラブル防止のためにライセンス契約を締結するようにしましょう。
口頭で約束した結果、後になって
- その利用方法は許していない。すぐに利用を中止して損害を賠償しろ。
- 請求された使用料が口頭で聞いていた使用料と違う。
とトラブルが起こってしまっては手遅れです。
書面という形で、何を約束したかを残しておくことで、余計なトラブルを回避することができます。著作権のライセンス契約について、詳しく知りたい方は、「著作権のライセンス契約とは?注意したいポイント3つを中心に解説!」をご覧ください。
また、著作権侵害にならない場合として、著作権者から利用許諾を得る以外に、著作権そのものを譲り受ける(譲渡してもらう)という方法があります。
5 権利を譲り受けた場合
著作権は譲渡可能な権利であることは既に説明したとおりです。著作権者から著作権の譲渡を受ければ著作権者になることができます。
(1)利用許諾と譲渡の違い
利用許諾は、単に著作物を利用することを許しているだけなので、著作権という権利が移動することはありません。著作権者は、利用許諾を与えても、自身で著作物の利用ができます。
他方、譲渡は、著作権を手放すことを意味しています。譲渡した元著作権者は、著作物を利用することはできなくなり、今の著作権者から利用許諾を得なければ著作権侵害となる可能性があります。
譲渡を受ける場合には、利用許諾を得る場合と同様に、トラブルを防止するために著作権譲渡契約を締結するようにしましょう。なお、ライセンス契約書と著作権譲渡契約書では、注意すべきポイントが異なります。著作権譲渡契約書について詳しく知りたい方は、「【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!」をご覧ください。
(2)著作者人格権
もっとも、著作権の譲渡を受けたとしても、著作物を完全に自由にできるわけではありません。なぜなら、著作者には、著作者人格権という権利が残るからです。
「著作者人格権」とは、著作者個人の名誉を守るために認められる権利です。あくまでも、著作者の名誉を守るために認められる権利のため、たとえ著作権を譲り受けたとしても著作者ではない他人が引き継ぐことはできません。
この著作者人格権があることで、著作者は、具体的には以下を行うことができます。
- 作品をいつ、どのように公表するかを決定すること
- 公表した著作物に名前を載せるかどうか、またどのような名前を載せるか(実名、変名など)を決めること
- 意に反する加工などをされないこと
- 著作者の名誉を害するような著作物の利用をされないこと
著作権の譲渡を受けると同時に、著作者からこれらの口出しをされないようにしたい場合には、「著作者人格権を行使しない」という項目を契約書に含めるようにしましょう。
このように、著作物を利用するには、著作権者から利用の許諾を得るか、著作権の譲渡をすることが基本です。もっとも、一部の行為に関して、許諾を得ることなく利用することが認められているものもあります。次の項目では、許諾を得ることなく利用できる場合について確認していきましょう。
6 許諾を得ることなく利用できる場合
著作権法によって一部の行為に対して、著作権は制限されています。著作権が制限される結果、著作権者から許諾を得ずに著作物を利用したとしても、著作権侵害とならないことになります。
(1)なぜ許諾を得なくても著作物を利用していいのか
著作権法は、文化を発展させるためにあります。
著作物の保護があまりに強すぎて、著作権者の許諾がなくては自由に著作物を利用できない状態にしてしまうと、新たな著作物を作成する際に既存の著作物の参照や利用が難しくなってしまいます。これでは、文化の発展は望めません。そのため、著作権者に不利益がない程度の、一定の条件付きで著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することを認めています。
(2)許諾を得ることなく利用できる7つの場合
著作権が制限され、著作権者に許諾を得ることなく利用できる場合として、下記の7つのケースに分けることができます。
- 私的利用
- 写り込み・検討過程など
- 調査研究・教育目的
- 福祉目的・非営利目的
- 報道目的、立法・司法・行政上の利用
- 美術の著作物の展示・譲渡など
- プログラムの著作物・電子計算機での利用
①私的利用
家庭などで個人的に著作物を複製(コピー)して使用する際は、著作権者から許諾を得ずに利用しても著作権侵害になりません。テレビ番組の録画、勉強のための参考書のコピーなどがこれにあたります。
ただし、違法サイトからのダウンロード等の複製は、私的利用であっても制限対象ではないため、著作権侵害となります。
②写り込み・検討過程など
屋外で撮影をした映像で、背景の看板や街で流れているBGMが偶然に撮影されてしまった場合は、その著作物について著作権は制限されます。著作権者に許諾を得なくとも、著作権侵害にはなりません。これらの写りこみに対して許可が必要になると、映像を自由に撮ることが難しくなってしまうためです。
また、キャラクター画像などの著作物を使って商品を作る際、検討段階の企画書でその画像を確認することで、スムーズに商品化が図れます。そのため、このような検討過程での著作物の利用に際して、著作権者に事前に許諾を得なくても、著作権侵害にはなりません。
③調査研究・教育目的
図書館や学校、博物館や美術館、学術機関での著作物の複製は、著作権者の許諾がなくとも著作権侵害にはなりません。これらの資料を利用することで、よりよい著作物を生み出すことにもつながるからです。また、適切な形式の引用や転載も認められています。
④福祉目的・非営利目的
視覚・聴覚に障害がある人のために、点字や映像の字幕処理、手話翻訳などをしたり、その著作物をインターネットで送信したり、貸し出したりすることは、無許諾でも著作権侵害にはなりません。
ただし未公開の著作物に限ります。既に同様の翻訳や複製がある場合には許諾を得なければいけない点には注意してください。
また、入場料や出演料を取らない形、宣伝目的ではない形での上演や演奏(非営利)も許諾は必要ありません。
⑤報道目的、立法・司法・行政上の利用
時事問題の論説、事件報道、政治演説、裁判手続き資料、行政庁の手続きや開示は、著作物を無断で利用したとしても著作権侵害にはなりません。
報道や公的機関の情報は広く知られることを目的としているため、制限を受けません。
⑥美術の著作物の展示・譲渡など
美術の著作物については、売買などにより作品を生み出した著作者と、その作品所有者が一致しないことがあります。このような場合には、著作物の所有者から展示の同意を得ていれば、著作者の同意を得なくても展示をすることができ、この展示が著作権侵害とはなりません。
また、美術展の案内パンフレットやWebサイトに著作物を掲載することもできます。
⑦プログラムの著作物・電子計算機での利用
市販のソフトウェアが著作物にあたる場合、購入者がそのプログラムを自分のパソコンにコピーして使うことができます。
ただし、違法な手段で複製されたもの(海賊版など)と知って入手したものは、著作権侵害となります。
これら著作権の制限についてさらに細かい条件や例外などがあります。さらに詳しく知りたい方は、【著作権の制限とは?無断で使用することができる7つのパターンを解説】をご覧ください。
7 小括
著作権侵害にならないように他人に作成してもらったコンテンツを利用するには、まずは、利用したいものが著作物にあたるものか考えましょう。
そして著作物にあたる場合には、誰が著作者や著作権者なのか、著作権の保護期間は切れていないか確認し、ライセンス契約で利用許諾を得るか、それとも著作権譲渡契約で著作権を譲渡してもらうか検討するようにしましょう。
また、利用方法や利用目的によっては、著作権者の許諾を得なくてもよい場合もあります。
これらを使い分けて、著作権侵害の重いペナルティを受けないようにしましょう。
8 まとめ
これまでの解説をまとめると、以下の通りです。
- 著作権とは、著作物を独占的に利用できる権利のことをいう
- 著作権侵害とは、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することである
- 著作権侵害にならないのは、①そもそも著作物ではなかった場合、②著作物であっても著作権がない場合、③権利者から利用の許諾を得た場合、④権利を譲り受けた場合、⑤許諾を得ることなく利用できる場合の5つである。
- そもそも利用したいものが著作物ではない場合、著作権を侵害していることにはならない
- 国や自治体が交付する法律や通達、裁判所の判決文などや、それを解説した公的機関の著作物を利用しても著作権侵にはならない
- 著作権の保護期間が切れた著作物も利用しても著作権侵害にはならない
- 権利者から著作物の利用について利用許諾を得れば、著作権を侵害せずに著作物を利用することができる
- 著作権者から著作権そのものを譲渡されれば権利を自由に行使できるが、著作者の著作者人格権は著作者に残り続けるため、名誉を損ねたりするような使い方などはできない
- 既存の著作物を参照したりすることで、新たな著作物を生み出し、文化を発展させる目的があるため、著作権は一定の範囲で制限される。
- 著作権が制限される条件を満たせば、著作権者から許諾を得ずに利用しても著作権侵害にはならない